🇬🇧 David Bowie (デヴィッド・ボウイ)
目次
スタジオ盤②
グラムロック末期~ジギー・スターダストとの決別
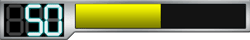
1973年 7thアルバム
『ジギー・スターダスト』に人格を取り込まれることを恐れたデヴィッド・ボウイは、前作アラジン・セインのツアー後に突如ジギー・スターダストをやめる宣言をし、ファンだけでなくスタッフやサポートメンバーを仰天させました。バックバンドのスパイダーズ・フロム・マーズも本作を最後に解散することになります。ボウイの作品に貢献してきたミック・ロンソンもボウイのもとを離れ、再び共演を果たすのは1990年代と、だいぶ先のこととなります。なおスパイダーズ・フロム・マーズもメンバーチェンジを行い、ドラマーがウッディー・ウッドマンジーからエインズレー・ダンバーに代わっています。ダンバーは後にジャーニーやホワイトスネイク等で活躍するドラマーです。
ジャケットにボウイと一緒に写った女性はモデルのツイッギー。プロデューサーには前作に引き続きケン・スコット。
本作はボウイのキャリア唯一の全編カバーアルバムです。ボウイが親しんできた1960年代楽曲のカバーで固めています。私はほとんど原曲を知らないので原曲との比較どうこうでは語れないのですが、恐ろしいほど高水準のボウイのオリジナルアルバム群と比べるとイマイチな印象は否めません。良い楽曲もあるんですけど、比較対象が悪すぎた…。
プリティ・シングスの「Rosalyn」で開幕。勢いのあるロックンロールで、結構攻撃的な歌唱ですね。ダンバーのドラムが良い感じ。ゼムの「Here Comes The Night」は速くなったり遅くなったり緩急のある楽曲。ボウイの吹くサックスがアクセントになっています。「I Wish You Would」はヤードバーズのカバー。まくし立てるような歌と、淡々としつつキンキンとした音を立てるギター特徴のロックンロールです。続いてシド・バレット時代ピンク・フロイドの「See Emily Play」。サイケデリックな楽曲ですが、これは良い具合に消化出来ている印象です。ボウイのダンディな歌に加えてスパイダーズ・フロム・マーズのメリハリのついた演奏もあり、原曲よりも好みです。狂う部分は狂っていますしね。続いてザ・モージョーズの「Everything’s Alright」。怪しげなイントロで始まりますが、そこからノリノリのロックンロールを展開。時折交える怪しげなフレーズがアクセント。「I Can’t Explain」はザ・フーのカバー。ヘヴィなサウンドですが、トーンはそこまで重くはなく、歌メロで魅せます。サックスによる味付けも印象的。
後半はイージービーツの「Friday On My Mind」で幕開け。キャッチーなメロディを歌いながら徐々にエンジンがかかってくる楽曲で、盛り上がる部分では怒り狂うかのように激しい。耳に残る良曲です。「Sorrow」はマージービーツのカバー。ストリングスが優美な、ポップな楽曲です。続いて、ロックンロールでノリの良い「Don’t Bring Me Down」はプリティ・シングスのカバー。そしてヤードバーズの「Shapes Of Things」はキャッチーなサビメロが印象的。歌うようなトレヴァー・ボルダーのベースや、後半のツインギターが良い感じ。「Anyway, Anyhow, Anywhere」はザ・フーのカバー。キャッチーな歌メロですが、サウンドは荒くてパンキッシュ。ダンバーのドラムソロが印象的です。最後にキンクスの「Where Have All the Good Times Gone」でキャッチーな歌を聴かせて終了。
全てが悪いというわけではなく所々にいいなと思う場面もあるのですが、1970年代のデヴィッド・ボウイの作品はどれも恐ろしいほど傑作揃いのため、普通な仕上がりの本作はそれらと比べるとイマイチな印象を強く持ちます。
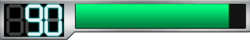
1974年 8thアルバム
グラムロック最後の作品だとか、グラムロックを脱した作品だとか、そのジャンル分けは人によって様々。スパイダーズ・フロム・マーズと袂を分かつ変化はあるものの音楽性は次作よりグラムロック時代に近く、また眼帯をしたハロウィン・ジャックという新たなキャラクターを演じるスタイルはグラムロックに位置づけても良いのではないかと思っています。なお本作のレコーディング前後くらいに拠点を米国に移しました。
ジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984』をテーマにしたコンセプトアルバムを目指したものの、遺族から許可が下りず、コンセプトを少し変えて発表したのが本作でした。半人半獣のジャケットが不気味ですね。退廃的な世界観を表現したアルバムは少し暗い雰囲気を纏ったロックンロールアルバムに仕上がっています。デヴィッド・ボウイのセルフプロデュース作で、ボウイ自身が楽器を演奏しているものも多いようです。参加ミュージシャンはマイク・ガーソン(Key)、ハービー・フラワーズ(B)、エインズレー・ダンバー(Dr)やトニー・ニューマン(Dr)など。
元々コンセプトアルバムなので一部の楽曲が繋がっていたりします。気味の悪い咆哮で始まる「Future Legend」は短いナレーションを加えて、最後は歓声とともに次曲「Diamond Dogs」へ繋がります。このタイトル曲はロックンロールナンバーで、ボウイの吹くサックスが賑やかなサウンドに仕立てます。適度な気だるさが気持ち良く、メロディもキャッチーですが、加工されたボーカルを含めてどこか不気味な雰囲気を醸し出しています。ここから3曲は組曲になっていて、まずは「Sweet Thing」。不協和音に始まり、まったりとした演奏にボウイがメロディの美しい歌を披露。全体に漂う退廃的な空気を保ちながら続く「Candidate」は、この暗鬱で不穏な空気を払拭するかのように徐々にテンポアップして盛り上がっていきます。狂気を交えながら最高潮まで盛り上がると、「Sweet Thing (Reprise)」でサックスが再び退廃的な雰囲気に引き戻します。美しい歌が終わるとノイジーで異様な緊張が漂う、とても不穏な空気に。そのまま始まる本作のハイライト「Rebel Rebel」。行進するかのようなリズムで、ひたすら反復される単調でエッジの効いたギターリフ。この印象的なギターはボウイが弾いています。歌も含めて耳に残るキャッチーさと、パンクのような攻撃性を持つ名曲です。
アルバム後半はバラード曲「Rock ‘N’ Roll With Me」に始まります。ガーソンのピアノが美しく、またダンディな低音ボーカルとキャッチーな中高音ボーカルを使い分ける歌で魅せます。コーラスワークも良い。続いて退廃的な「We Are The Dead」で静かに暗い雰囲気に。電子ピアノの音は綺麗なのにこんなにも不穏なのは暗い歌のせいでしょうか。バンド演奏が歌を引き立てながら、どんどん闇深くなっていく感じです。そしてドラマチックな「1984」は痺れる名曲です。焦燥感を煽るような不穏な感じと、キャッチーでメロディアスな歌を引き立てる仰々しいストリングスのアンバランス感。ボウイの感情たっぷりの歌は魅力だし、演奏は鳥肌が立つほどスリリング。とにかくカッコ良い楽曲です。続く「Big Brother」は小説『1984』の独裁者の名で、コンセプトとしての使用を遺族に却下されたものの、前曲と合わせてその名残でしょうか。ホーンを用いた渋いサウンドに、ソウルフルな歌唱。次作のテーマであるアメリカンソウルへの接近が見られます。そのまま途切れず続くラスト曲「Chant Of The Ever Circling Skeletal Family」はあまりに狂気じみた感じ。洗脳されたのか、最後の最後には壊れた機械のように「Bro bro bro bro…」と連呼して終わります。あまりに不気味なのですが、レコードだと無限に再生され続ける仕掛けが施されているようです。だから「Ever Circling」なんですね。
サウンドプロダクションのせいか少し取っつきにくさも感じるものの、退廃的な雰囲気は魅力的で、また佳曲揃いの名盤です。
アメリカ時代~ソウルミュージックへの傾倒

1975年 9thアルバム
アメリカに渡ったデヴィッド・ボウイは前作『ダイヤモンドの犬』のツアーの途中から突如ソウル路線にシフト。そして『The Gouster (ザ・ガウスター)』というアルバム制作を進めますが、ジョン・レノンとの出会いによって「Fame」という名曲とビートルズの名アレンジ「Across The Universe」という素晴らしい楽曲を生み出します。2つの突出した名曲を生み出したボウイはこれら楽曲を加えて選曲を変更、そして『ヤング・アメリカンズ』というアルバムを発表したのでした。「Fame」はボウイ念願の全米1位獲得シングルとなりました。そして幻となったアルバム『ザ・ガウスター』は、2016年のボックスセットで日の目を見ることになります。余談ですが、ずっと『ザ・グースター』だと思っていました…。
プロデューサーには久しぶりのトニー・ヴィスコンティ。サポートメンバーも充実していて、本作で活躍したカルロス・アロマー(Gt)はしばらくボウイを支えることになります。
オープニングを飾る表題曲「Young Americans」ではソウルフルに歌うボウイの姿が。デヴィッド・サンボーンのサックスが華やかに彩り、ファンキーなリズム隊にゴスペル風のコーラスも加わってアメリカンソウルに染まった1曲です。キャッチーなメロディと同じフレーズの反復がやけに耳に残る名曲ですね。途中にビートルズの「A Day In The Life」の一節が出て来てニヤリとします。この楽曲もジョン・レノンの影響を受けているかもしれませんね。「Win」は心地良い倦怠感のある、まったりしたサウンド。大きなインパクトを持つ前曲に比べるとやや地味な印象ですが、浮遊感のあるギターが気持ち良い。続いて「Fascination」はキャッチーでファンキーな楽曲。グルーヴ感の溢れるサウンドも良いですが、同じキーワードを繰り返すコーラス隊とボウイの掛け合いがとても耳に残ります。中々魅力的な1曲です。「Right」はR&B風の大人びた楽曲です。メロウなサックスと控えめなギター、そしてパーカッションがリズミカルに心地良く演奏。そしてゴスペル風のコーラスがボウイのソウルフルな歌以上に際立っています。
アルバム後半は「Somebody Up There Likes Me」で幕開け。サックスを中心とした心地良いサウンド。そしてしゃがれ声で力強く歌うソウルフルな歌唱がお見事で、黒人になりきっています。続いてビートルズのカバー「Across The Universe」。原曲はジョン・レノンがボーカルを取る繊細な1曲でしたが(そしてレノンの楽曲ではトップクラスの名曲!)、力強くソウルフルに歌うボウイのアレンジは原曲とはまるで別物。メロディの良さを活かしつつソウルフルな歌唱は鳥肌もので、この名曲に新たな魅力を与えました。ラストの「Nothing’s gonna change my world」の連呼とか痺れるほどカッコ良く、実に名アレンジだと思います。ちなみにレノンもギターやコーラスで参加。ストリングスで優美な「Can You Here Me」でまったりとした後は、ジョン・レノンとの共作となる「Fame」。本作においては異色ですが、これがあるから本作が名盤になったという。ファンク要素が強いグルーヴィなサウンドに、どこか奇妙でふざけた感じがあるもののキャッチーなメロディ。一度聴いたら耳について離れない、とにかく強烈なインパクトを放ちます。面白くて魅力的な名曲です。
アメリカンソウルに傾倒した作品です。ジョン・レノンとの出会いがなければ、平均以上の楽曲が並んで小綺麗に纏まった作品に仕上がったことでしょう。そんな『ザ・ガウスター』を覆して、「Fame」と「Across The Universe」という異色の突出した2曲をぶちこんだ『ヤング・アメリカンズ』は、追加した楽曲がアクセントとなってこのアルバムを名盤に押し上げていると思います。
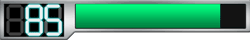
1976年 10thアルバム
前作『ヤング・アメリカンズ』発表後、映画『地球に落ちてきた男』の撮影を挟んで制作された本作。ジャケットアートはその『地球に落ちてきた男』のワンシーンを取っているそうです。前作に引き続きソウル路線を継承していますが、アメリカンな黒人ソウルになりきった前作とは異なり、ソウル・ファンクを消化してロックと融合、白人ソウルとしての名盤を完成させました。ヨーロッパの雰囲気も持つ表題曲には、ドイツのバンドクラフトワークへの傾倒も見え始めています。
デヴィッド・ボウイがサックスやミニムーグ等も演奏。サポートメンバーは、カルロス・アロマー(Gt)、アール・スリック(Gt)、ジョージ・マーレイ(B)、デニス・デイヴィス(Dr)、ロイ・ビタン(Key)、そしてプロデューサーも兼ねるハリー・マスリン(Synth)。アロマーがファンキーなリズムギターを担い、スリックがロック寄りのリードギターと分担しています。
表題曲「Station To Station」は10分に渡る大曲。名曲の始まりを予感させる序盤は、汽車のようなSEと、スリックのギターがメタリックな音色を奏でます。そして列車がゆっくり進み始めたかのようにグルーヴ感のあるリズム隊が爽快。途中からボウイのソウルフルな歌唱が加わります。後半は列車が驀進するかのようにリズムが加速。終盤はキャッチーな歌メロが魅力的です。長い上に同じ旋律や同じ単語をくどいほど反復するのに、効果的な場面転換もあって飽きが来ないどころか中毒性があります。ライブだとよりスリリングですね。続く「Golden Years」はファンキーな楽曲で、前作の延長上にあります。グルーヴ感抜群のサウンドに、ボウイのソウルフルな歌唱でひたすら反復する歌詞がやけに耳に残ります。カッコ良くて、そして心地良い中毒性を持っています。「Word On A Wing」はバラード。強い哀愁を纏ったボウイの迫真の歌が響きます。また、ビタンによるピアノの音色によって、洗練された印象に仕上がっています。
アルバム後半に差し掛かり、愉快な雰囲気の「TVC 15」。3パターンくらいのフレーズをそれぞれひたすら反復するのですが、これがキャッチーで耳に残ります。ノリの良いリズミカルな演奏も良いですね。そして「Stay」は後半のハイライト。グルーヴィなリズム隊が特に際立つ名曲で、ファンキーで跳ねるようなギターにグルーヴ感の強いベース、パーカッションが気持ちの良い演奏を繰り広げます。そして歌には少し哀愁があります。そしてラストの「Wild Is The Wind」は、映画『野生の息吹』の主題歌のカバーだそうです。哀愁あるメロディをソウルフルに歌います。中々渋い印象です。
アルバム全編を通して、歌詞やリズム等に反復が見られ、これが妙に耳に残るのでやみつきになります。前作からのソウル路線にロック要素を持ち込んで魅力的な作品に仕上げました。
アメリカでの生活はドラッグまみれで、薬物に蝕まれて身体もボロボロになってしまいました。この頃「シン・ホワイト・デューク (=痩せて青白い公爵)」という新たなキャラクターを生み出しますが、痩せこけたボウイのルックスは痛々しいほどです。この『ステイション・トゥ・ステイション』を生み出したボウイは、ドラッグの浄化のため、そしてクラフトワークを生んだ地を訪ねるためにドイツへと渡りました。そこで、ベルリン三部作と呼ばれる新たな傑作群を生み出すことになります。
ベルリン三部作
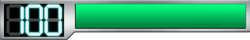
1977年 11thアルバム
通称「ベルリン三部作」と呼ばれる傑作群の1作目。ドラッグの浄化のためにドイツのベルリンへと渡ったデヴィッド・ボウイは、後に音楽界の巨匠として名を馳せる、元ロキシー・ミュージックのブライアン・イーノと組んで本作の制作に取り掛かりました。ただ、クレジットを見るとわかるように大半の楽曲はボウイの作曲。クラフトワークやタンジェリン・ドリームといったジャーマンロック勢を好んで聴き、影響されたそうです。唯一「Warszawa」にのみブライアン・イーノの名前が並びます。プロデューサーはトニー・ヴィスコンティ。名プロデューサーとして名を馳せるブライアン・イーノは、ここでは作曲やシンセサイザーのプレイヤーとしての関与だったみたいですね。
本作と同年に次作『ヒーローズ』をリリースし、またその一方で友人イギー・ポップのアルバムプロデュースにもかかわります。こちらも1977年に2作リリースし、そのプロデュースと多くの楽曲の作曲にボウイが関わりました。非常に意欲的に活動し、そして出来上がった作品も名盤だらけ。ボウイのキャリアの中でも特に突出した才能を発揮した一年でした。
さて本編は「Speed Of Life」で始まります。オープニング曲がインストゥルメンタルで驚かされますが、前作から大きく変化したこのアルバムの方向性を示しています。しかしこの楽曲の実にカッコいいこと。シンセを中心にしたサウンドは憂いや哀愁を強く滲ませ、聴いていると切ない気持ちになります。前半は2曲を除いて一応ボーカル曲を並べ、後半はほぼ全編に渡ってインストゥルメンタルとなります。でもボーカル曲についても、歌メロを聴く作品というよりは、シンセサイザー等によって作られた音楽観を味わうのがメインといった趣です。2曲目「Breaking Glass」からはボーカル曲。前作を踏襲したファンキーなリズム隊、特にジョージ・マーレイのベースが強いグルーヴを生み出しますが、楽しい感覚よりも寂寥感を感じるのはわざとらしいシンセのせいでしょうか?また、独特な音処理を施したデヴィッド・デイヴィスのドラムも印象的です。続く「What In The World」では疾走感のあるサウンドにピコピコ鳴るシンセが印象的。軽快な演奏が爽快です。そして「Sound And Vision」、これが素晴らしい。大半は演奏で、シンセサイザーとギターを中心に作る世界観を楽しむ楽曲です。とても美しくて、また寂寥感に溢れています。ボウイのメランコリックな低音ボーカルもカッコ良いんですよね。サックスもボウイが担当。「Always Crashing In The Same Car」も歌はあるものの、どちらかといえば神秘的な演奏がメイン。心地良いけど寂しい感覚が同居します。続く「Be My Wife」は「妻になってくれ」と歌う切ない1曲です。ピアノがアクセントとなり演奏はリズミカルですが、メロディは憂いに満ちています。「A New Career In A New Town」はインスト曲。わざとらしいシンセも虚しく、どこか哀愁を感じさせるのはハーモニカのせいでしょうか。
後半、レコードでいうB面は、一部でコーラスも入るもののほぼ全編インストゥルメンタル。そのB面1曲目「Warszawa」はボウイのインストゥルメンタルの最高峰でしょう。ボウイとブライアン・イーノの共作となるこの1曲は退廃的で、喧噪とは無縁の荒廃した静寂といったイメージ。どうしようもなく暗くて、重く寒々しい空気を漂わせていますが、それでいて美しさすら感じられます。なおタイトルとなったポーランドの都市ワルシャワは、この時期は東西冷戦の東側に位置する社会主義国家。本作の制作地ベルリンも冷戦によって壁で分断された、冷戦最前線の地。後追い世代なので冷戦当時の空気感はわかりませんが、この楽曲のように暗く重たいものだったのではないかと勝手に想像しています。続く「Art Decade」は西ベルリンをイメージした楽曲らしいです。前曲から引き続き、静けさと暗鬱な空気を纏っています。前曲よりは少し神秘的な感覚が加わっています。そして「Weeping Wall」、邦題「嘆きの壁」。ベルリンの壁のことでしょう。ヴィブラフォン/シロフォンはボウイの演奏で、これらに加え不気味なシンセやノイジーなギターが不穏な空気を作り出し、焦燥感を煽り立てます。騒がしくはないですが、どうしようもなく不安になります。ラスト曲「Subterraneans」は東ベルリンをイメージしたそうです。ひんやりとしたシンセに、テープの逆再生も用いたのか少し不気味なSE。暗鬱な空気に乗るメロウなサックスが渋さを追加し、歌というより楽器のようなコーラスが少し救いだったり。とは言え、最後まで空気は晴れないままアルバムを締め括ります。
シンセサイザーを全面導入して前作までのソウル路線から一転した本作。寒々しい空気が全体を覆いますが、素晴らしい出来です。自身の最高傑作『ジギー・スターダスト』にも匹敵する、最高傑作候補の一角です。また、後のニューウェイヴ・ムーブメント形成にも大きな影響を与えました。
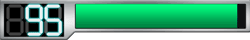
1977年 12thアルバム
旧邦題『英雄夢語り』。写真家の鋤田正義によって撮影された、ロック史でもトップクラスのイケメンジャケットが目を惹きます。ジャケットに写ったデヴィッド・ボウイをよく見てみると、右目と左目で瞳孔の大きさが異なることに気づきます。これは小さい頃にガールフレンドを巡る喧嘩で負傷し、瞳孔が開き切ってしまったのだとか。また先天性のオッドアイで、この写真ではモノクロなのでわかりませんが、左右の眼の色も異なります。
前作と同様にブライアン・イーノと組んで制作した本作。プロデューサーも前作に引き続きトニー・ヴィスコンティ。前半に歌メロ、後半にインストゥルメンタルを固めた構成は前作と似ていますが、よりロック感が強くなっています。
躍動感溢れる「Beauty And The Beast」で始まります。デヴィッド・デイヴィスのドラムがダイナミックなほか、全体的にハードな仕上がりでバンドサウンドを感じさせます。でも歌メロは女性コーラスも含めてキャッチーな印象は強く、取っ付きやすいオープニング曲ですね。続く「Joe The Lion」も同様に躍動感があって好印象です。歌はキャッチーだけど緊迫感に満ちていて、明るい雰囲気ではないですけどね。キレのあるギターが中々スリリングです。そして3曲目には超名曲「”Heroes”」。デヴィッド・ボウイのキャリアで一番の名曲です。この楽曲、私の結婚式でも使わせて頂いたので思い入れも強いです。ボウイとブライアン・イーノの共作で、ギターはキング・クリムゾンのロバート・フリップが奏でます。「壁際に立って、頭上で銃声が響く中、僕たちはキスをした」と歌う歌詞の一説は、ベルリンの壁の砲塔の下で落ち合う恋人をレコーディングスタジオから目撃し、そこに着想を得たというエピソードがあります(実はトニー・ヴィスコンティが不倫相手と会っていることにインスピレーションを得たのだと、後に語っています)。また、1987年に、西ベルリンの広場でボウイがこの楽曲を歌った際、壁の向こう側から数千人が聞こえたというエピソードもあり、冷戦当時に東西に分断されたドイツを勇気づけた1曲でもあります。2年後にめでたく壁は崩壊しドイツは東西統一を果たしました。「僕らはヒーローになれる、一日だけなら」と歌う歌詞は、聴く者を勇気づけ、また終盤のヒステリックな歌唱は胸に響きます。この素晴らしい名曲を、ジャケットに描かれたイケメンがイケボで歌うんですから、背景を知らなくたってボウイに理想のヒーロー像を抱いてしまいますね。そして続く「Sons Of The Silent Age」ではまったりとしたメロウなサウンド。ですがサビで突如ヒステリックになる歌は強い哀愁を帯びていて、切ない気分にさせます。「Blackout」ではまたテンポアップ。躍動感のあるロック色の強い1曲で、途中捲し立てるような歌い方をはじめ、程よい緊張感に満ちてスリリングです。ここまで歌メロ中心の前半パートでした。
アルバムは後半に入り、インストゥルメンタルパートに突入(一部でコーラスは入りますが)。第二次大戦中のナチスドイツの兵器、世界初の弾道ミサイルV2ロケットを歌った「V-2 Schneider」。でも歌っているテーマの割には重たさはあまりなくて、リズミカルで結構ノリが良い。タカタカタッ…タカタカタッという小気味良いドラムも爽快ですが、ボウイのサックスとマーレイのベースが特に良い味を出していて好みな1曲です。続いて前作『ロウ』のように暗く重たい「Sense Of Doubt」。低音が重たいピアノに、寒々しくて寂寥感のあるシンセの音色。救いのない暗鬱なこの楽曲には、冷たい風が吹き渡るような効果音も入っています。そして幻想的な楽曲「Moss Garden」。ボウイの奏でる琴の音色に和の要素を感じますが、ボウイは来日時に京都をよく訪れていたそうです。続く「Neuköln」は再び暗鬱な雰囲気。シンセの作る重く冷たい空気に、時折割って入るボウイのメロウなサックスが渋くて痺れます。そしてラスト曲「The Secret Life Of Arabia」は歌が出てきます。哀愁に満ちているものの、重たい空気を払拭する躍動感のある演奏で気分を変えてすっきりと締めてくれます。
アルバムトータルで見ると楽曲の纏まり具合で前作に僅かに劣るものの、しかし本作にはボウイの最高傑作たる超名曲「”Heroes”」があり、どちらも甲乙つけがたい傑作です。やはり本作も、最高傑作候補の一角に挙げたい素晴らしい名盤です。
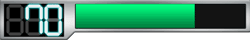
1979年 13thアルバム
旧邦題『ロジャー (間借人)』。ベルリン三部作の3作目となります。今作でもブライアン・イーノが参加しているもののアンビエントからは遠ざかり、作風は前2作よりも明るくポップになった印象です。スイスと米国ニューヨークで録音されました。デヴィッド・ボウイとトニー・ヴィスコンティの共同プロデュースで、ライブ盤『ステージ』でサポートしたメンバーを中心にした布陣で臨んでいます。
ちなみに2017年にヴィスコンティが再ミックスしていますが、音の分離がくっきりして魅力を増した印象です。
オープニング曲「Fantastic Voyage」から前作とは雰囲気を変えてポップで優しい曲調です。ボウイの歌は程よい哀愁を伴っていてメロディアス。アルバム全体的にひねたポップソングが多い中、この楽曲はストレートにメロディが良いです。「African Night Flight」はプリミティブな雰囲気全開の、非西欧的で実験的な1曲。まくし立てるような早口ボーカルのインパクトが強いですが、それ以上にアフリカンなリズム隊が強く印象に残ります。ポストパンクムーブメントにおいて、多くのバンドが非西欧的な音楽を探求しロックとの融合を図りますが、ボウイのこのアプローチもその一環でしょうか。「Move On」は軽快に疾走するリズムが爽快です。デニス・デイヴィスのスネアを使わないドラムがダイナミックな印象。取っつきにくい呪術的なコーラスも入っているものの、主旋律は比較的キャッチーで、サビの力の入った歌唱もカッコ良い。「Yassassin」はトルコ語で「Long Live (○○万歳!)」の意味。トルコ語のタイトルが示すように、オリエンタルで怪しげな魅力を放つ独特のメロディが中々のインパクト。演奏はファンクやレゲエを取り入れてリズミカルで、イスラム風のメロディに合っています。続いて「Red Sails」はポップ曲。ひねていて変なメロディですが、明るくてノリが良くキャッチーな仕上がりです。
後半のオープニングはシングル曲「DJ」。リズミカルなサウンドに淡々とした歌が続きますが、サビのメロディは耳に残るキャッチーさがあります。間奏ではメタリックなギターを中心に実験的なアプローチがなされています。続いて「Look Back In Anger」。タイトルを見るにオアシスの超名曲「Don’t Look Back In Anger」が浮かびますが、こちらは真逆で「怒りを込めて振り返れ」。疾走感のある演奏に、ナルシー気味な歌が中々キャッチーな印象です。「Boys Keep Swinging」はリズム隊を強調して躍動感に満ちています。ベースはグルーヴィに動き回り、ドラムは前進するかのような力強さがあります。反面メロディは少し弱いかも。「Repetition」は実験的な楽曲。ブンブンと低音が鳴り響くものの軽い印象のリズム、これがひたすら反復するせいか妙な中毒性があります。楽曲そのものはそこまでキャッチーでもないんですけどね。ラスト曲は「Red Money」で、これもリズムを強調した変な感じのポップソングです。メロディが弱いこともあって、個性的なリズムが更に際立ちます。
実験的でひねたポップソングが並びます。突出した名曲はないものの、面白いアプローチの佳曲が詰まった作品だと思います。














