🇬🇧 Jeff Beck (ジェフ・ベック)
レビュー作品数: 6
スタジオ盤
第1期ジェフ・ベック・グループ
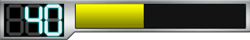
1968年 1stアルバム
孤高のギタリストこと、ジェフ・ベック。フルネームをジェフリー・アーノルド・ベックといいます。イングランドのロンドン出身で、1944年6月24日生まれ、2023年1月10日没(享年78歳)。
日本ではエリック・クラプトン、ジミー・ペイジと並んで3大ギタリストと呼ばれるジェフ・ベック。3人が3人ともヤードバーズに所属していました。そんなヤードバーズを脱退したベックはミッキー・モストとプロデュース契約を結んでソロシングルをリリースした後、自身のバンドを結成します。ロッド・スチュワート(Vo)とロン・ウッド(B)、ニッキー・ホプキンス(Key)、エインズレー・ダンバー(Dr)のラインナップでしたが、エインズレーが脱退してミッキー・ウォーラー(Dr)が加入。改めてこのラインナップで本作が制作されました。なお本作はレッド・ツェッペリン(以下ZEP)のヒントになったとされますが、ジェフ・ベックとレッド・ツェッペリンの共通のマネージャーだったピーター・グラントにより否定されています。影響の有無はさておきハードロック黎明期に重要な役割を果たした作品であることは間違いありません。音は古臭いですけどね。
オープニング曲は「Shapes Of Things」。ヤードバーズのカバー曲です。ヘヴィでブルージーなサウンドに、ロッドのハスキーボイスが響き渡ります。ドラムが強烈。「Let Me Love You」も渋い。ロッドのボーカルとジェフのギターが掛け合いを繰り広げます。「Morning Dew」はボニー・ドブソンのカバー。緩急あって、ゆったりとしたパートからの盛り上げ方がスリリング。暴れ回るリズム隊が良いです。続く「You Shook Me」はブルースミュージシャン、ウィリー・ディクソンのカバーで、ZEPもカバーした楽曲です。正直、衝撃度はZEPの方が数段上ですが、こちらはピアノやオルガンによる華やかさがあります。「Ol’ Man River」はロッドのしゃがれた渋い歌声でしっとりと聴かせます。
「Greensleeves」は英国のフォークソングのインストゥルメンタルアレンジ。柔らかいアコギの響きが美しく、癒されます。続く「Rock My Plimsoul」は強烈にブルージーな1曲。渋いサウンドにロッドの歌声が映えます。「Beck’s Bolero」はメンバーがとても豪華です。ザ・フーのキース・ムーン(Dr)に、後のZEPのジミー・ペイジ(Gt)にジョン・ポール・ジョーンズ(B)が参加。序盤は大人しいですが、後半は別物のように化けます。スリリングに暴れ回る魅力的な1曲です。「Blues De Luxe」はスローテンポのブルージーな楽曲。ニッキーのピアノが聴きどころです。時折拍手が響きますが、ライブ録音なのでしょうか。そしてラスト曲「I Ain’t Superstitious」はウィリー・ディクソンのカバー。ギターとリズム隊の掛け合いが中々スリリングです。
ハードロックバンドの元祖になり損ねた、ハードロック黎明期の作品。アイディアは革新的だったそうですが、今聴くとやはり古いなぁと思います。
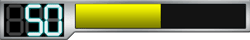
1969年 2ndアルバム ※The Jeff Beck Group (ジェフ・ベック・グループ) 名義
前作同様ミッキー・モストによるプロデュース。前作リリース後にジェフ・ベックはミック・ウォーラー(Dr)とロン・ウッド(B)を解雇し、トニー・ニューマン(Dr)とダグラス・ブレイク(B)が後任として加入。しかし力量の低さからダグラスを解雇して、解雇したロンを再度呼び戻します。そんなゴタゴタに嫌気がさしたのか、本作のリリースを前後してニッキー・ホプキンス(Key)は脱退、ロッド・スチュワート(Vo)とロンも脱退してフェイセズに参加、ジェフ・ベック・グループは崩壊することになります。
なおジャケットに描かれたリンゴの絵画はルネ・マグリットの『La Chambre d’écoute』という作品だそうです。
エルヴィス・プレスリーのカバー「All Shook Up」で開幕。ドラムが炸裂し、ベースがうねり、ロッドのハスキーボイスがシャウトします。そして何よりジェフのヘヴィで荒々しいギターが良い!ハードロックの様相を整えて、前作より洗練された印象です。ニッキーのピアノが荒さを唯一和らげます。続く「Spanish Boots」も、ブルース色はかなり強いけどハードロック寄りな感じ。「Girl From Mill Valley」はインストゥルメンタル。ニッキーのしんみりとしたピアノと、小さく鳴るオルガンが感傷的な気分にさせます。「Jailhouse Rock」はイントロからかなりヘヴィなギターが重たい。全体的に音質は悪いですが、荒々しくてカッコ良いです。ロッドの声は荒々しいサウンドにも埋もれず、強い存在感を放ちます。ややスローテンポですが王道ロックンロール…と思ったらこの楽曲もエルヴィス・プレスリーのカバーでした。
「Plynth (Water Down The Drain)」はノリの良い楽曲です。反復するリフやファンキーなリズムなど次々と雰囲気が変わっていく楽しい楽曲です。続く「The Hangman’s Knee」は重量感のあるサウンド。ゴリゴリとした重低音が響き、かと思えば金切音のようなギターに圧倒されます。そして「Rice Pudding」は7分半に渡るラスト曲。これもパワフルで、ヘヴィなリフが爆裂します。トリッキーなリズムが妙なフックを引っ掛け、スピードも緩急つけて変化に富んでいます。
前作よりも荒々しくなり、ハードロック色が強くなりました。魅力も倍増していると思います。
本作の後ジェフ・ベック・グループが空中分解したため、ジェフ・ベックは元ヴァニラ・ファッジのティム・ボガートとカーマイン・アピスと新バンド結成を画策。しかし不運にもジェフが交通事故を起こして入院し、そうこうしている間にボガートとアピスは別バンドのカクタスを結成。彼らとの新バンド結成は数年後を待つことになります。
第2期ジェフ・ベック・グループ
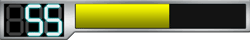
1971年 3rdアルバム ※The Jeff Beck Group (ジェフ・ベック・グループ) 名義
交通事故から完治したジェフ・ベックは新たなメンバーを集いました。ボブ・テンチ(Vo)、クライヴ・チャーマン(B)、マックス・ミドルトン(Key)、コージー・パウエル(Dr)を迎えてジェフ・ベック・グループを再度結成。日本では第2期ジェフ・ベック・グループと呼ばれています。ジェフ自身のセルフプロデュース作。
オープニングを飾る「Got The Feeling」はファンキーな楽曲です。グルーヴ感抜群のサウンドで、ボブのソウルフルな歌声も含めてブラックミュージックへの傾倒が見られます。また中盤のピアノはジャジーでもあります。自然とリズムに乗せられてしまいますね。「Situation」はイントロのトリッキーなリズムから加速して、ファンキーでノリノリなサウンドを奏でます。後半は即興的な演奏を繰り広げます。中々スリリングでカッコ良い。「Short Business」は自由に動き回るベースが気持ちの良いグルーヴを生みます。続く「Max’s Tune」はマックス・ミドルトン作のインストゥルメンタル。グルーヴが心地良い前3曲とは異なり、静かな空間に渋い音色が響き渡ります。メロウでムーディな演奏はジャズを聴いているかのようです。
アルバム後半は「I’ve Been Used」で幕開け。コージーのドラムが炸裂し、ヘヴィなギターが唸りを上げます。「New Ways / Train Train」はジェフのヘヴィなギターとコージーのドラムの掛け合いが魅力的。抜群のグルーヴ感が気持ち良い。そして最後を飾る「Jody」はバラード曲。序盤しっとりと歌い上げるボブのソウルフルな歌声は妙な説得力があります。序盤の演奏ではドラムが非常にパワフル。間奏はギターが踊るかのように軽やかで、間奏が終わるとリズムカルな楽曲に変貌します。
ソウルやファンクとロックを融合した作品で、黒っぽい印象を抱きます。全体的にグルーヴィでノリの良い楽曲に溢れていて、自然と身体がリズムを刻みます。
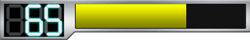
1972年 4thアルバム ※The Jeff Beck Group (ジェフ・ベック・グループ) 名義
前作でプロデューサーも兼ねていたジェフ・ベックは、スティーヴ・クロッパーをプロデューサーに迎えて本作を制作。メンバーは前作と同じラインナップで、ジェフ・ベック(Gt)、ボブ・テンチ(Vo)、クライヴ・チャーマン(B)、マックス・ミドルトン(Key)、コージー・パウエル(Dr)。ジャケットの色から通称『オレンジ・アルバム』と呼ばれるそうです。
オープニング曲「Ice Cream Cakes」はコージーのヘヴィなドラムプレイで開幕。ゆったりとしたテンポでジャズっぽいサウンドに乗る、ボブのソウルフルな歌声が渋いです。独特のグルーヴ感が気持ち良い。「Glad All Over」はファンキーなロックンロール。ご機嫌なノリで歌われるこの楽曲はとてもノリがよく、楽しい気分にさせてくれます。「Tonight I’ll Be Staying Here With You」はボブ・ディランのカバー。ボブのソウルフルな歌声、黒っぽいコーラスなど、渋さに溢れています。続く「Sugar Cane」はマックスのピアノを主体に、ギターがグワングワンとしています。途中からご機嫌なパーカッションが前面に出てきて、所々笑いながら歌うボーカルと、和やかなスタジオの空気が伝わってくるかのようです。「I Can’t Give Back The Love I Feel For You」はインストゥルメンタル。初っ端ヘヴィなサウンドに驚かされますが、その後はブルージーなギターが歌うかのようにメロディラインをなぞります。
アルバム後半は、マックスの軽快なピアノが爽快な「Going Down」で始まります。ピアノに負けじとジェフのギターも張り合っているのですが、それよりもリズム隊、特にクライヴの地を這うような強烈なベースが良い味を出しています。「I Got To Have A Song」はスティーヴィー・ワンダーのカバー。こちらもクライヴのベースやコージーのドラムが爽快なグルーヴ感を生み出しています。「Highways」もグルーヴが強烈。時折スポットの当たるアツいギターソロが聴きどころです。ラスト曲「Definitely Maybe」はインストゥルメンタル。ジャジーでメロウなこの楽曲は、喋っているかのような、文字どおり歌っているかのような音を出すジェフのギタープレイが秀逸です。この路線で次作以降スタイルを築き上げることになります。
グルーヴ感に溢れる前作を洗練させ、更に次作への布石となるギターインスト曲も秀逸。ジェフ・ベック・グループ時代では一番出来の良い作品だと思います。
本作のツアーで不満を感じたジェフは、メンバーを解雇してカクタスのティム・ボガートとカーマイン・アピスに接近。ベック、ボガート&アピスを結成することになります。
ソロ活動 (フュージョン期)

1975年 5thアルバム
ジェフ・ベックはギタリストとしては優れていたもののバンドとしてはいずれも長続きせず、念願のティム・ボガートとカーマイン・アピスと組んだベック、ボガート&アピスも結局1枚のオリジナルアルバムで解散。そしてたどり着いた先がインストゥルメンタルでした。ビートルズを手掛けたジョージ・マーティンをプロデューサーに迎え、マハヴィシュヌ・オーケストラに影響を受けたフュージョン寄りの作風です。このアプローチがとても魅力的なのです。サポートにはマックス・ミドルトン(Key)、フィル・チェン(B)、リチャード・ベイリー(Dr)。
なお当初の邦題は『ギター殺人者の凱旋』。このダサさ、ハードロックじゃないんだから…。そんな邦題は最近は原題のとおり『ブロウ・バイ・ブロウ』になっています。
全曲がインストゥルメンタルです。オープニング曲「You Know What I Mean」はファンキーなナンバー。緩くもグルーヴ感のあるフレーズをひたすら反復しながら、その上でギターが爽快感を生み出します。リズムがトリッキーですね。「She’s A Woman」はビートルズのカバー。レゲエのようなリズムに乗せてまったりとした雰囲気です。ギターがメロディラインを奏でますが、時折トーキングモジュレーターを用いてワウワウ喋っているかのよう。「Constipated Duck」はメロディよりも演奏を重視した1曲。ギターとキーボードが自由で即興的な演奏を繰り広げる一方で、リズム隊も強い存在感を示します。「Air Blower」はファンク色が強い1曲。軽快なリズムに乗せた演奏はどんどんとテンションが上がっていき、繰り広げられる演奏バトルはとてもスリリングです。終盤では一気に熱が冷めたかのように静けさが訪れ、メロウでムーディな雰囲気で締めます。続く「Scatterbrain」はリチャードのドラムソロから始まる1曲で、まくし立てるかのような高速ギターやキーボードをはじめ、終始凄まじく緊迫感に満ちたスリリングな演奏に圧倒されます。そんな中グルーヴ感のあるベースが、スリリングな演奏を一緒に楽しもうよと誘ってくれているかのようです。
「Cause We’ve Ended As Lovers」はスティーヴィー・ワンダーの作曲で、『哀しみの恋人達』の邦題で知られるジェフの代表曲です。哀愁のバラードを、ボーカルパートの代わりを担うギターが泣かせにきます。ジェフのギターは感情豊かですね。渋くて、魅力的な楽曲です。続く「Thelonius」もスティーヴィー・ワンダー作で、全体的に愉快な雰囲気です。「Freeway Jam」はジャムセッションのノリで楽しそうです。リズム隊に支えられ、ギターが歌うようにメロディを奏でます。フィルのベースも結構存在感があります。最後に8分半近い「Diamond Dust」。楽曲の繊細で哀愁漂う雰囲気をオーケストラが引き立てます。しっとりと浸らせてくれる楽曲でアルバムを締めます。
ジェフ・ベックの最高傑作に挙げられることの多い本作。個人的にはフュージョン路線を更に押し進めた次作に軍配が上がるものの、本作も高いクオリティで楽しませてくれます。
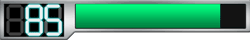
1976年 6thアルバム
最高傑作と名高い前作『ブロウ・バイ・ブロウ』のフュージョン路線を押し進めた作品で、本作も前作に並ぶ傑作として知られます。個人的にはこちらが最高傑作だと思っています。ジャケットもカッコ良いですね。
プロデューサーは前作に引き続きジョージ・マーティン。なお名曲「Blue Wind」のみ、ヤン・ハマー(Key)がプロデュース。このヤン・ハマーのサウンド面への貢献が大きいと思います。マックス・ミドルトン(Key)、ウィルバー・バスコム(B)、ナラダ・マイケル・ウォルデン(Dr)、リチャード・ベイリー(Dr)らが参加。
フュージョン色の濃厚な「Led Boots」で開幕。ジェフの強烈なギターと、手数が多い上に炸裂音があまりに強烈なナラダのドラム。またヤンのスペイシーなシンセサイザーなど、名プレイヤーによる凄まじく緊迫感に溢れた演奏はぶっ飛んでいて、とてもカッコ良いです。演奏バトルという言葉がぴったり。続く「Come Dancing」はファンク色の強い1曲で、グルーヴ感に溢れた気持ちの良いノリが特徴。ホーンセクションも加わって華やかですが、時折ざらついた荒い音でハッとさせます。終盤高らかに鳴るギターの音色が爽快です。「Goodbye Pork Pie Hat」はしっとりと聴かせるメロウなナンバーで、ドラマーはリチャード・ベイリーが担当。ジェフのギターがフィーチャーされていて、ブルージーなメロディを奏でます。とても渋く、そして表現力豊かなギターの音色に惹かれます。「Head For Backstage Pass」は初っ端からウィルバーのベースソロに圧倒されます。リチャードの刻む軽快なドラムはどんどんとテンションが上がっていき、他の楽器も合わせて激しい演奏を繰り広げます。3分足らずですが密度の濃い1曲です。
そしてアルバム後半のオープニングを飾る「Blue Wind」、これが超名曲なのです。この楽曲でヤンはシンセだけでなくドラムも担当。タイトルにも表れているような、疾走感に溢れる爽快な1曲。ウィルバーの地を這うようなベース、ジェフの高らかな音色のギターに呼応するかのような、シンセベースと手数の多いドラムはヤンによるものだそうで。さらにヤンはスペイシーなシンセの速弾きで張り合うという。笑 テンションが高いのですが爽やかさも合わせ持っていて、とてもカッコ良いです。本楽曲以降はドラムがナラダに戻ります。続いて「Sophie」はゆったりとしたパートと、異様にテンションの高いパートが交互にやってきます。特にギターとシンセの主導権の奪い合いがとてもスリリングです。「Play With Me」はスリリングな演奏の傍らで、メロディアスな音色も聴かせてくれます。メロディに浸ろうとするとナラダのドラムの手数の多さに驚かされるという…。ラスト曲「Love Is Green」はしっとりとした楽曲。激しい演奏のあとのひと息といった感じで、メロウな楽曲をじっくり聴かせてアルバムを締め括ります。
多くの楽曲で演奏バトルが繰り広げられています。全編インストゥルメンタルですが、歌なしでも飽きないどころか凄まじいテンションの高さに圧倒されます。スリリングな名盤です。
関連アーティスト
第1期ジェフ・ベック・グループのメンバー、ロッド・スチュワート(Vo)のソロ。
第1期ジェフ・ベック・グループのメンバー、ロッド・スチュワート(Vo)とロン・ウッド(B)の移籍先。
第2期ジェフ・ベック・グループのメンバー、コージー・パウエル(Dr)のソロ。
『ワイアード』で共演を果たしたヤン・ハマーの所属していたフュージョンバンド。
類似アーティストの開拓はこちらからどうぞ。


















