🇬🇧 The Rolling Stones (ザ・ローリング・ストーンズ)
レビュー作品数: 13
スタジオ盤
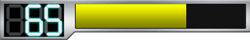
1967年 6thアルバム(英)/8thアルバム(米)
ローリング・ストーンズは1962年に英国ロンドンで結成されました。2019年現在に至るまで57年間一度も解散していない、ロック界稀にみるご長寿バンドです。結成当初のメンバーはミック・ジャガー(Vo)、キース・リチャーズ(Gt/Vo)の幼馴染2人に、ブライアン・ジョーンズ(Gt)、イアン・スチュワート(Pf)(直後にメンバーから外れロードマネージャーとサポートメンバーを務めます)、ビル・ワイマン(B)、チャーリー・ワッツ(Dr)。よくビートルズと比較されますが、ビートルズがR&Bを独自解釈でどんどん進化させていき、また多重録音や逆再生等の手法を用いてアルバム主体のサウンドづくりに変遷していくのに対し、ローリング・ストーンズはR&Bのスタイルを固持し、またライブが主体でアルバムはバンドサウンドを追求したものになっています。また港町リヴァプール出身のビートルズと、大都会ロンドン出身のローリング・ストーンズという比較もあるかもしれませんね。
ローリング・ストーンズは英国と米国でそれぞれ独自リリースが進み、本作『サタニック・マジェスティーズ』からようやく英米で足並みが揃います。そのせいもあって英国だと本作は6thアルバム扱いですが、米国では8thアルバム扱いとなっています。
本作はビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』に影響を受けたことが明らかで、発売当初は酷評されたそうです。ジャケットアートとかまさにそんな感じですね。楽曲も、ローリング・ストーンズらしいR&B志向からは離れた、スペイシーなサイケデリックロックが展開されます。ちなみにバンドメンバーが大麻所持で逮捕されるなど(ミック、キース、のちにブライアン)、メンバー自身もズタボロで混迷極めていた時期の一作でした。ただし今改めて聴くと、サイケ全盛期の時代に沿った作品の一つとしてみることもできます。
「Sing This All Together」で開幕。儀式のような怪しげなパーカッションやコーラスが印象的ですが、ミックの歌うメロディは意外とキャッチーです。続く「Citadel」は気だるげな楽曲。キースの奏でる歪んだ音のギターがルースな感じですが、ビルの唸るベースはメリハリをつけてカッコ良い。時折キンキンとした音が耳障りですが、サイケデリックな印象を強めています。「In Another Land」はビルがボーカルを務めます。ボーカルは強く加工されて不気味ですが、アコースティック基調のサウンドは牧歌的で優しいです。歌の終わった後にいびきを収録している謎の演出…。続く「2000 Man」は前半で一番魅力的な佳曲です。牧歌的なアコギに始まり、前半は哀愁漂う歌メロが切ない。しかし楽曲後半は別の楽曲をくっつけたかのように明るいトーンに変わりらハモンドオルガンも鳴る軽快なバンド演奏が楽しげです。咳払いで始まる「Sing This All Together (See What Happens)」は8分半に及ぶ、怪しげで実験的な楽曲です。よくわからないパーカッションに、メロディも無く咆哮するだけなので、ジャングルを彷徨っているような印象を抱きます。終盤に1曲目の歌メロをリプライズ。
レコードB面に入り、本作ではずば抜けた名曲の「She’s A Rainbow」が始まります。CM等でもよく耳にする楽曲ですね。ストーンズらしくないですが、心が洗われるような美しさ、そして物悲しさを合わせ持った名バラードです。キャッチーだけど哀愁に溢れるメロディに加えて、エレピの音色が美しい。なお、後にレッド・ツェッペリンのメンバーとなるジョン・ポール・ジョーンズがストリングスアレンジを担当しています。「The Lantern」は気だるげな1曲。ピアノとアコギが優しいサウンドを奏で、アンニュイな歌メロがまったりと癒してくれます。「Gomper」は実験的な楽曲。民族音楽的なパーカッションに、太鼓タブラや弦楽器サロードなどインドの伝統楽器も用いて、エスニックな雰囲気です。そして「2000 Light Years From Here」は個人的に「She’s A Rainbow」に次ぐ名曲です。不協和音が鳴り響いた後に始まるメロトロンの音色が、まるで宇宙空間へと引きずり込むかのような、不思議で不気味な浮遊感を醸し出しています。ミックの囁くような歌は、メロトロンの不気味な響きのせいで妙に不安を煽ってくるんですよね。スペイシーでスリリングな楽曲です。最後に「On With The Show」で明るいトーンに。歌はラジオのように少し遠くから聞こえる感じ。陽気な雰囲気ですが、終盤に向かうにつれサイケデリックな狂気性が顔を見せます。
酷評されることもある作品ですが、メロディアスな良曲もありサイケ作品として中々魅力的で、駄盤として切り捨てるにはあまりに勿体ないです。

1968年 7thアルバム(英)/9thアルバム(米)
自身の音楽性を変えてしまった前作『サタニック・マジェスティーズ』によって、ファンの間には不安が広がっていました。危機感を覚えたミック・ジャガーは、バンドの方向性を決定づけるためにジミー・ミラーをプロデューサーに招き、その結果として本作からしばらく続く傑作群を生み出すことに成功。ブルース志向が復活した本作はローリング・ストーンズの傑作の一つに挙げられます。これまではブライアン・ジョーンズが主導してきた面もありましたが、大麻の使用や鬱病など、心身の不調が深刻に悪化したために本作での貢献はかなり少なかったようです。
アートワークに採用された便所の落書き写真はリリース前にひと悶着あって、レーベル側から「いかがわしい」と拒否されてシンプルなジャケットに変更してリリースしたそうです。現在ではオリジナルの便所の写真が採用されるようになりましたが、50周年記念でまた差し替え後のシンプルなジャケットが復活したみたいですね。
1曲目の「Sympathy For The Devil」からいきなりの名曲。ベースとパーカッションでサンバ調の陽気なリズムをひたすら反復し、その上をミック・ジャガーがキャッチーなメロディを歌います。途中から加わる「Woo, woo」という合いの手も延々と続き、これが強烈な中毒性を持っているんですよね。更にキース・リチャーズの弾く、切れ味抜群の鋭利なギターも加わりスリルは最高潮に。自然と身体が動き出す楽しい楽曲です。ここからアコースティックな楽曲が続くのですが、まずは「No Expectations」。アコギによるまったりとした演奏、しかしミックの歌は物憂げな雰囲気を醸し出します。ちなみにスライドギターはブライアンが弾いており、本作における数少ない貢献だったとか。「Dear Doctor」はカントリー色の強い1曲。アコギに加えてハーモニカの音色が郷愁を誘います。「Parachute Woman」はアコギとエレキが絡み合い、気だるいロックンロールを展開します。ハーモニカが加わることにより、泥臭い印象をより強めます。「Jigsaw Puzzle」はキースのスライドギターが心地良い浮遊感を醸し出します。ゲストのニッキー・ホプキンスによるピアノも良いアクセントになっていますね。
アルバム後半のオープニングを飾るアップテンポ曲「Street Fighting Man」は、ローリング・ストーンズの代表曲です。キースの弾くアコギからチャーリー・ワッツの力強いドラムが加わり、ミックの歌が始まって、ビル・ワイマンのベースも加わる…という、この始まり方がとても良いです。軽快でノリも良く、自然とリズムに乗せられてしまいます。途中シタールが鳴り響いて異国情緒を加えますが、これはブライアンが弾いています。「Prodigal Son」も小気味良く軽快。でも前曲に比べると音数は少なく、ジャカジャカかき鳴らすアコギが前面に出ています。「Stray Cat Blues」は泥臭い楽曲。力強いドラムが印象に残ります。「Factory Girl」は牧歌的な楽曲で、昔の村のお祭りのようなイメージがあります。マンドリンの音色も影響しているのかな?そしてラストに控える「Salt Of The Earth」が名曲。ミックとともにキースも歌いますが、哀愁のあるメロディがとても魅力的なのです。終盤にはワッツ・ストリート・ゴスペル合唱団による壮大なコーラスも加わり、感動的なラストを迎えます。
アコースティックな楽曲が中心で、締めるところは締めるのですが、比較的ゆったり聴くことのできる作品です。所々に素晴らしい名曲を散りばめていて、でも「全曲が名曲!」とはいかずに出来にムラがあるのがローリング・ストーンズのアルバム群の歯がゆいところです。…が、どこか完璧になりきれないところも彼ららしいというか、聴く側に緊張感を強いることなく、緩く聴かせてくれるところも好きなんですけどね。
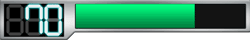
1969年 8thアルバム(英)/10thアルバム(米)
ビートルズの『Let It Be (なすがままに)』が有名なせいで、『Let It Bleed (血を流せ)』のタイトルはパロディだとか二番煎じだとも言われますが、実際には本作の方が先のリリースでした。可愛らしいケーキのジャケットとは裏腹に、物騒なタイトルと泥臭くて黒っぽいサウンド。ローリング・ストーンズの名盤の一つです。
前作から深刻な心身不調に陥っていたブライアン・ジョーンズはついに脱退し、代わってミック・テイラー(Gt)が加入。メンバーはミック・ジャガー(Vo)、キース・リチャーズ(Gt/Vo)、ビル・ワイマン(B)、チャーリー・ワッツ(Dr)、そして新加入のミック・テイラーは「Honky Tonk」と「Live With Me」の録音に参加。
なお、脱退したブライアンは脱退1ヶ月後に自宅のプールで溺死しているのが見つかります。また本作リリース後のツアーにおいて、会場警備員によって黒人青年が殺害されるという悲しい出来事もありました(オルタモントの悲劇)。またミック・ジャガーと恋人のマリアンヌ・フェイスフルが麻薬所持で捕まるなど、この頃のローリング・ストーンズは負の側面が最高潮だったようです。しかし逆境に立ちながらも本作をリリースして、名声を獲得することになります。
メリー・クレイトンをゲストボーカルに迎えたオープニング曲「Gimme Shelter」は本作のハイライトです。ベトナム戦争をうたったこの楽曲は、ミック・ジャガーとメリー・クレイトンのデュエットが展開されます。特にメリーのソウルフルな歌唱はとても魅力的で、ローリング・ストーンズの奏でる黒っぽい雰囲気を更に増幅させています。キースの弾くブルージーなギターをはじめ、渋い演奏も魅力です。「Love In Vain」はロバート・ジョンソンのカバーで、とても渋い1曲。アコギを中心としたノスタルジックなサウンドに、とてもブルージーな歌が響き渡ります。続く「Country Honk」は、本作には収録されなかったシングル曲「Honky Tonk Women」のカントリーアレンジ。アコギに加えてフィドルの音色が、牧歌的で村のお祭りみたいな雰囲気を出しています。ビルのベースソロで始まる「Live With Me」はドラムが単調な印象を作りますが、サポートミュージシャンのボビー・キーズによるサックスが良いアクセントになっています。続いて表題曲「Let It Bleed」。意外なほどあっさりしていてアルバムタイトルを冠するほどの名曲だとは思えないのですが、ピアノも入ってゆったりと聴ける1曲です。ピアノは6人目のストーンズことイアン・スチュアートが弾いています。
レコードB面(アルバム後半)の1曲目「Midnight Rambler」はブルージーなサウンドが印象的な名曲です。ノリの良い演奏はグルーヴ感抜群で、途中で加速したりゆったりとしたり、即興的でライブ感のある楽しい楽曲です。ライブの定番曲でもあり、ライブの方がよりスリリングで楽しめます。何気に7分近くもあるんですよね。「You Got The Silver」はキースが歌うルースな1曲。脱退直前のブライアンが生前最後にレコーディング参加した楽曲だそうです。続く「Monkey Man」はイントロのピアノとビブラフォンの音色が、美しくも不穏な印象を与えます。ですがブルージーなバンド演奏は結構ノリノリで、楽曲が進むと楽しげな雰囲気に。ミックはシャウトしっぱなしですね。そしてラスト曲「You Can’t Always Get What You Want」はゴスペル風の大作。ロンドン・バッハ合唱団による神々しいコーラスで始まった後、泥臭いロックが展開。ノリは良いけどごちゃついたパーカッションに乗せて、ソウルフルな女性ボーカルが賑やかで、なかなかに楽しい名曲なのです。ラストのコーラスは神々しくて鳥肌ものです。
泥臭さを極めて、そしてルースなロックを展開するストーンズらしい作品です。『ベガーズ・バンケット』から続く傑作群の一つで、ストーンズに興味を持った方はこちらも聴くべきでしょう。

1971年 9thアルバム(英)/11thアルバム(米)
レコード会社といざこざがあった後に設立したプライベートレーベル「ローリング・ストーンズ・レコード」よりリリース。ジミー・ミラーによってプロデュースされた本作は、これまで同様にブルース路線を踏襲しています。全英1位だけでなく全米1位も獲得し、ストーンズのこれまでの売上記録を更新して大ヒットしました。
アンディ・ウォーホルが手掛けた、ジーンズが有名なジャケットアート。レコード時代は実際にジッパーが付いていたというんだから凝っていますね。更に内ジャケットにはブリーフを穿いた男性の股間の写真という、しょうもないこだわりもロックですね。笑
ローリング・ストーンズ屈指の名曲「Brown Sugar」で始まります。お得意のロックンロールですが、キース・リチャーズの弾くイントロのギターリフがとてもカッコ良い(リフのアイディアは珍しくミック・ジャガーらしいですが)。そのミックの歌うメロディもキャッチーでノリが良く、「イェー イェー イェー フォーゥ!」と賑やかでとても楽しいので、口ずさみたくなりますね。サポートミュージシャンのボビー・キーズが吹くサックスも、ノリを演出するのに貢献しています。続く「Sway」はスローテンポでブルージーな楽曲。チャーリー・ワッツのドラムをはじめ力強い演奏が印象的です。終盤はピアノとストリングスで少し壮大な感じ。「Wild Horses」はカントリー調のバラード。アコギでゆったり聴かせますが、こういう緩く聴けるところもストーンズの魅力だと思っています。アコギだけでなくスライドギターも心地良さを提供してくれます。メロディアスで憂いのある歌も魅力的ですね。「Can’t You Hear Me Knocking」は7分を超える本作最長の1曲。前半はブルージーで少しハードなギターが主導し、サポートミュージシャンのビリー・プレストンのオルガンが唸ります。中盤からはガラリと雰囲気が変わり、サックスとドラムを中心にスリリングな演奏を展開。ミック・テイラーの長尺のギターソロも魅力的です。「You Gotta Move」はフレッド・マクドウェルのカバー曲(更にその元ネタは伝統的な黒人霊歌だそう)で、コテコテのブルースです。スローテンポでダルそうな楽曲を披露します。
アルバム後半はキャッチーな「Bitch」で幕開け。Superflyもカバーしていましたね。前曲がダルい感じだったため、ピシッと引き締まった印象を受けます。リズミカルな上にホーンが賑やかで、ノリが良くて楽しい。ギターリフもカッコ良いですね。「I Got The Blues」は3拍子のゆったりとした演奏にホーンやオルガンの味付けが心地良い。そして何と言ってもメロディラインが美しく、哀愁漂う歌は切ない気分にさせます。魅力的な楽曲ですね。「Sister Morphine」は事故に遭いモルヒネを欲する男の苦しみを描いた歌です。そんな世界観を表現したか、哀愁漂うアコギと、靄がかかったような幻惑的なエレキギターが織り成すサウンドを展開。エレキギターはゲスト参加のライ・クーダーが弾いています。ドロドロした印象。続く「Dead Flowers」はほのぼのとして晴れやかな雰囲気の良曲です。心地良いカントリーロックですね。ラスト曲「Moonlight Mile」は雄大な雰囲気で、少し切なさを感じさせる楽曲です。ブルージーですが、後半からはストリングスによって盛り上がります。なんとなく夜空を思い浮かべるサウンドです。
緩くまったり聴ける楽曲を中心に、所々引き締まったカッコいい楽曲が光ります。『ベガーズ・バンケット』から続く名盤群の一つですが、特に名曲が多くてストーンズ入門向きです。個人的には次作が最高傑作と思っていますが、その次作に次ぐ名盤です。
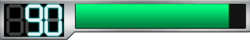
1972年 10thアルバム(英)/12thアルバム(米)
全67分、発売当初はレコード2枚組(CD化により1枚)だったという大ボリュームな作品です。ローリング・ストーンズは『ベガーズ・バンケット』から本作までの4作に最高傑作だという評価が集まりますが、個人的には本作が最高傑作だと思っています。その理由は、収録時間が長くてストーンズの世界観に浸れる時間が長いから。笑 全18曲の、バラエティ豊富な楽曲揃いだからこそ、長くても楽しく聴けるのでしょう。但し全曲が名曲とは言いません。ラフで緩い楽曲群を適度に聞き流しつつほどよく浸りながら、時々現れる魅力的な瞬間にハッとするという聴き方がとても楽しいのです。
前作に引き続きジミー・ミラーがプロデュース。レコーディングは最初フランスで行われたものの、メンバーの多くがドラッグ漬けになったり、その雰囲気に嫌気が差したチャーリー・ワッツが途中から来なくなったりと、色々ゴタついていたようです。そして米国ロサンゼルスに場所を移してレコーディングを再開。長時間かけたレコーディングの末に沢山のマテリアルが集まり、そこから選別してこの傑作が出来上がったようです。
レコード時代のA面オープニング「Rock Off」はストーンズお得意のロックンロール。前作の「Brown Sugar」のようにキャッチーなイントロで引き込んでくる名曲で、キース・リチャーズのギターリフが最高ですね。ノリが良く、軽快なピアノや華やかなホーンなどバックの演奏陣も賑やかで、聴いていると楽しい気分になります。続く「Rip The Joint」も賑やかさを保ちながら、更にスピードを上げてとても爽快です。ミック・ジャガーの歌は終始シャウト気味で、サポートミュージシャンによるピアノやサックスもご機嫌。高いテンションで楽しげな空気に、リスナーをも強引に巻き込んでくるかのよう。「Shake Your Hips」はチャーリーのカチャカチャ鳴るパーカッションが印象的です。リズムギターと合わせてノリの良いグルーヴで楽しませます。テンション高めな3曲とうって変わって、「Casino Boogie」は気だるげなロックンロール。脱力感がありますが、肩の力を抜いて心地良く聴けます。そして前半の一つの山場である「Tumbling Dice」。緩い雰囲気を纏いつつも、ゴスペル風のコーラスワークも加わって明るく賑やかな楽曲です。聴いていて楽しい気分になれますね。ちなみにビル・ワイマンの代わりにミック・テイラーがベースを、チャーリーの代わりにプロデューサーのジミー・ミラーがドラムを叩いています。
レコード時代のB面、「Sweet Virginia」ではアコギに変わって緩くカントリー風の演奏。ほのぼのとしていますが、チャーリーのドラムは力強い印象。サビはコーラスが分厚く、農家の人たちが仲良く皆で歌ってるかのようなイメージが浮かびました。「Torn And Frayed」も牧歌的な雰囲気で、ゆったりと心地良い演奏に浸れます。続く「Sweet Black Angel」はアコースティックなサウンドがノスタルジックな空気を生み出している印象。ですが、終始鳴り響くギロの音が楽しげな雰囲気へと変えています。「Loving Cup」は、サポートのニッキー・ホプキンスの弾くピアノが哀愁を誘います。歌メロも少し憂いを帯びていますね。後半はホーンが主導して賑やかな雰囲気へと変わります。
続いてレコードC面。CD化で1枚になりましたが、当時レコード2枚目のオープニングを飾った「Happy」はキースがボーカルを取る1曲。これがとても良いんです。口ずさみたくなるようなキャッチーなメロディラインに加えて、演奏もご機嫌なので聴いていて楽しい。歌詞は「ハッピーでいたいから愛が欲しいんだ」という、シンプルでストレートな内容です。「Turd On The Run」はテンポの速い軽快な楽曲。前曲から続くノリノリなテンションを保ちます。続く「Ventilator Blues」は一気にトーンを落として、緩いテンポとスッカスカな音で渋いスタート。途中からホーンが加わって盛り上がってはいきますが、全体的にゆるーい印象です。そのまま途切れず続く「I Just Want To See His Face」はプリミティブな印象のパーカッションをはじめ、未開の文明っぽい怪しげな雰囲気が終始漂います。続く「Let It Loose」はメロウなバラード。ゴスペル風のコーラスが飾る歌メロは哀愁が漂っていて、また時折響くピアノの音色が美しい。しみじみと聴ける良曲です。
ここからレコードD面に突入。「All Down The Line」はアップテンポのロックンロールです。賑やかでご機嫌な演奏と歌で、聴いていると晴れやかな気分になれます。でも爽やかではなく泥臭い印象なのがストーンズらしい。「Stop Breaking Down」でテンポを落として、緩いロックンロールを展開。キースとミック・テイラーのとてもブルージーなギターが心地良い雰囲気を作ります。続く「Shine A Light」はドラマチックなバラード。ピアノとオルガン、ギターの絡む演奏は感情を高ぶらせ、そしてメロディアスな歌が刺さる刺さる。ゴスペル風のコーラスも終盤盛り上げてくれます。名曲です。そしてラスト曲「Soul Survivor」はミドルテンポの楽曲。ミックの力強いシャウトが特徴的ですが、緊張を強いずほどよく肩の力を抜いて聴けます。
米国のブルースを自分達のものにしていますが、彼らは英国人なんですよね。聴いていて英国特有の湿っぽさや憂いは感じず、米国寄りの泥臭いブルースを聴かせてくれます。色々な魅力的な顔を見せてくれる、とても心地よい18曲。ストーンズが好きになった人にはたまらない1枚ではないでしょうか。

1973年 11thアルバム(英)/13thアルバム(米)
全体的にゆったりとした雰囲気で、ロックンロールしている楽曲が少ないのが本作の特徴です。でもローリング・ストーンズ屈指の名バラード「Angie」をはじめとしたメロディアスな楽曲が多く、そして数少ないロックンロール曲に「Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)」と「Star Star」という名曲を携えていて、個人的にはお気に入りの1枚です。
ジャマイカで録音されましたが、レゲエ等のジャマイカ音楽の要素は特に見られません。引き続きジミー・ミラーのプロデュース作ですが、本作で最後となります。
「Dancing With Mr. D」で開幕。オープニング曲ですが、気だるい雰囲気で緩く始まります。「デーンセン デーンセン」の連呼が心地良いですね。グルーヴ感のあるベースはビル・ワイマンではなくミック・テイラーが弾いています。続く「100 Years Ago」はメロディアスな1曲。憂いのあるメロディラインと、ゲストのビリー・プレストンの弾くクラビネットの装飾によって感傷的な雰囲気を持っています。そしてなんといってもミック・テイラーのギターがカッコ良く、ワウワウ唸るファンキーなプレイは聴きどころです。終盤はテンポアップしますが、1曲の中でコロコロと表情を変えるスリリングな楽曲ですね。続く「Coming Down Again」はキース・リチャーズの歌うメロディアスなバラード。ゲストのニッキー・ホプキンスの弾くピアノが哀愁のメロディと良く合っています。しっとりと聴かせた後は、少しテンポを上げて「Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)」。イントロのギターリフから惹き込まれます。テンポ自体はそこまで速くないものの、チャーリー・ワッツの躍動感のあるドラムが作り出すビートがノリノリです。ミック・ジャガーの歌うメロディはキャッチーで、またホーンによる華やかな演出や黒っぽいコーラスワーク、ファンキーなギターも心地良いですね。そして本作のハイライト「Angie」。これが涙を誘う素晴らしいバラードで、この1曲が本作を大きく引き立てているのは間違いありません。アコギとピアノによる哀愁漂うメロディに乗せて、ミックの渋く切ない歌がじんわり染み入ります。後半はストリングスも加わり、感傷的な気分を高めてくれます。
アップテンポ曲「Silver Train」でノリ良くアルバム後半の幕開け。ご機嫌なロックンロールで、音が分厚く賑やかです。これと次曲はベースが良さげですが、これもビルではなく今度はキースが弾いているという。笑 「Hide Your Love」はピアノがリードする、緩いテンポの気だるいロックンロール。ピアノはミック・ジャガーが弾いているのだとか。そして「Winter」はメロディアスな楽曲で、憂いに満ちたメロディが魅力的なんです。前半はゆったりと癒してくれますが、後半はストリングスが加わってドラマチックな印象です。「Can You Hear The Music」はリズムも反復する歌詞も、ファンク色の強いグルーヴィな楽曲。ですが木管の音色によって牧歌的な印象も持ち合わせています。最後はアップテンポな名曲「Star Star」で締めます。ノリの良いロックンロールで、イントロからご機嫌。当初「Star Fucker」と名付けられる予定だったのがNGとなり、今のタイトルになったそうです…が、サビでは「star fucker」を連呼してますけどいいんでしょうか?笑 有名人と寝たがる女を批判した歌だそうですが、そんな歌詞はさておきキャッチーでノリの良い楽曲が魅力的で、個人的には「Angie」と双璧をなす1曲です。「Star Star」はライブで更に化けるため、本作においては「Angie」に軍配が上がりますね。
ロックンロールよりはバラード寄りの本作ですが、魅力的な楽曲が多くてオススメです。スタジオ盤では『メインストリートのならず者』に次いで2番目に好きです。
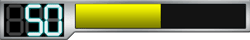
1974年 12thアルバム(英)/14thアルバム(米)
これまでの名盤の数々をプロデュースしてきたジミー・ミラーに代わり、グリマー・ツインズがプロデュース。このグリマー・ツインズとは、ミック・ジャガーとキース・リチャーズのことで、2人の共同プロデュースの際はこの名称を用いたそうです。ホーンセクションやストリングスを排してストレートなロックンロールを追求した、シンプルな作品に仕上がっています。
なお、本作を最後にミック・テイラーが脱退。黄金期とも言えるミック・ジャガー(Vo)、キース・リチャーズ(Gt/Vo)、ビル・ワイマン(B)、チャーリー・ワッツ(Dr)、ミック・テイラー(Gt)の最後のラインナップ作となりました。
オープニング曲「If You Can’t Rock Me」からノリの良いロックンロールを展開します。ストレートかつパワフルな楽曲で、キレのあるギターリフに、チャーリーのドコドコ鳴るドラムが印象的です。キャッチーですが音質に少し難あり。続く「Ain’t Too Proud To Beg」もアップテンポ曲。音数は多いはずですが、これまでの作品に比べると若干シンプルで隙間がある印象です。ビリー・プレストンの弾くピアノやクラビネットが良い感じ。そして本作のハイライトとも言える表題曲「It’s Only Rock ‘N Roll (But I Like It)」が続きます。「知ってるさ、ただのロックンロールだって。だが大好きだ!」という分かりやすい歌詞。ロックンロールを愛し、奏で続けるローリング・ストーンズのためにあるような1曲ですね。メロディが抜群にキャッチーで聴きやすく、またノリの良い賑やかな演奏も爽快で、自然とリズムに乗せられます。オープニングから3曲連続でアップテンポが続きましたが、「Till The Next Goodbye」ではアコギを主体にしっとりと聴かせます。反復が多いですが、憂いのあるメロディと優しいアコースティックサウンドが心地良く癒してくれます。終盤加わるピアノも美しいですね。「Time Waits For No One」もメロディアスな1曲で、これまでとは違ってあまり泥臭くなくクリアな印象を抱きます。哀愁漂う歌メロも良いですが、ミック・テイラーによる歌うようなギターソロが美しいんです。
ここからアルバム後半に突入しますが、後半はパンチ力が弱い気がします。まずは晴れやかな雰囲気のロックンロール「Luxury」で幕を開け、続く「Dance Little Sister」は後半では数少ない魅力的な楽曲。キレのあるアップテンポのハードロック曲で、終始響く低音ギターサウンドが渋カッコよく、ノリも良くて爽快です。「If You Really Want To Be My Friend」は憂いのあるメロディアスな1曲。ゆったりとしていて心地良い雰囲気ですが、6分強が若干長く感じるかも。「Short And Curlies」はルースなロックンロールで、ミック・ジャガーの気だるげな歌唱が心地良い。イアン・スチュワートの弾くピアノが良いアクセントになっています。ラスト曲「Fingerprint File」はファンキーな楽曲。抜群のグルーヴ感を発揮しますが、音質の悪さが気になります。
表題曲は魅力的なのですが、アルバム全体でパッとする曲が少なくて、個人的には聴くことは少ないです。音質の悪いサウンドプロダクションも個人的にはイマイチ…。

1976年 13thアルバム(英)/15thアルバム(米)
脱退したミック・テイラーに代わり、元フェイセズのロン・ウッド(ロニー・ウッド)が後任ギタリストとして加入しました。但し本作でロンがギターを弾いているのは僅か2曲。最終的にメンバーには選ばれませんでしたが、ハーヴィ・マンデルやウェイン・パーキンスらも気合いの入ったギターを弾いています。
ファンクやレゲエを取り込んだ、バラエティ豊富な仕上がりとなっています。前作に引き続き「グリマー・ツインズ」ことミック・ジャガーとキース・リチャーズによるセルフプロデュース作。ちなみにローリング・ストーンズの全オリジナルアルバムで最も曲数の少ない作品だそうです。
オープニング曲「Hot Stuff」はファンキーな1曲で、ストーンズらしくないのですが、これがとてもカッコ良い。個人的には本作を聴く理由はこのオープニング曲にあります。ひたすら同じフレーズの反復なのですが強い中毒性があり、ファンクのグルーヴ感に満ちていてとても気持ち良い。ハーヴィ・マンデルがギター参加していますが、このギターがカッコ良いんですよね。そして「Hand Of Fate」はストーンズらしさを取り戻した気だるげなロックンロール。悠々とカッコ良いギターソロを弾くのはウェイン・パーキンスですが、キースのリズムギターも負けじとカッコ良いリフを奏で続けます。珍しく(?)ビル・ワイマンのベースが強調されていて、楽曲にアクセントを与えています。続く「Cherry Oh Baby」はレゲエ曲でビックリ!レゲエミュージシャンのエリック・ドナルドソンのカバー曲で、これもクセになる中毒性があります。レゲエの気だるげで心地良いリズムと、コーラス含めて猥雑な感じの歌が結構楽しいです。そして名バラード「Memory Motel」。珍しく7分もある大曲です。憂いのある魅力的なエレピはキースが弾いており、また歌メロもミックだけでなくキースと交互に歌っています。哀愁があって、しっとりとした雰囲気がたまりません。
レコードB面、アルバム後半に入り「Hey Negrita」。ファンク色の強い楽曲でやはりストーンズらしくないのですが、反復されるフレーズが作り出すノリが心地良かったりします。チャーリー・ワッツの力強いドラムに乗せて、ロンとキースがギターの掛け合いを披露。猥雑な歌も含め、ノリノリで楽しい楽曲です。「Melody」はビリー・プレストンの弾くピアノが主体のジャジーな1曲。でもオシャレな演奏とは裏腹に、俗っぽい印象が抜けないのはミックの普段どおりの歌い方のせいでしょうか。笑 後半はホーンも加わり華やかです。続いてバラード曲「Fool To Cry」。ファルセットを多用した楽曲で、ゆったりとした雰囲気に満ちています。ラスト曲「Crazy Mama」は晴れやかなミドルテンポのロック曲。ミックもギターを弾き、またベースはキースが弾いています。音数の多さに加えてコーラスが賑やかな雰囲気を演出し、明るく本作を締めます。
ローリング・ストーンズのキャリアの中では割と異色な作品ですが、バラエティ豊富で意外と面白いです。最初の1枚というよりは、いくつか聴いてローリング・ストーンズの新たな魅力を知りたくなったときが本作の聴き時ではないかと思います。

















