🇬🇧 The Smiths (ザ・スミス)
レビュー作品数: 6
スミス紹介動画
動画にまとめていますので、ぜひご視聴ください!
スタジオ盤
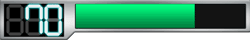
1984年 1stアルバム
英国で絶大な人気を誇るバンド、スミス。モリッシー(Vo)、ジョニー・マー(Gt)、アンディ・ルーク(B)、マイク・ジョイス(Dr)の4人組で1982年に英国マンチェスターで結成しました。ニューヨーク・ドールズのファンクラブを立ち上げた、定職に就かないライターだったモリッシー。そんなモリッシーの読者でもあったミュージシャンのジョニー・マーがモリッシーに声をかけて結成したそうです。
スミスが凄いのは、不良やスクールカーストの頂点に立つ者の音楽だったロックを、定職に就かないゲイというスクールカースト最底辺のモリッシーが歌ったこと。またメンバーも全員労働者階級でした。サッチャー政権下の英国で、不況や失業に苦しむ若者たちに大いに希望を与えました。スミスの活躍によりカッコ悪いことがカッコ良いという考えが支持され、またギターポップな音楽性も後発に多大な影響を与え、オルタナティヴロック/インディーロックの素地を作りました。プロデューサーとしてジョン・ポーターを起用。
「Reel Around The Fountain」で、静かに穏やかに幕を開けます。マイクのシンプルなドラムが淡々とリズムを刻んで存在感を発揮。メロディアスなギターや、優しくメランコリックで憂いのあるモリッシーの歌が切ないですね。オルガンも良い味付けです。続く「You’ve Got Everything Now」では、アンディとマイクのリズム隊2人がグルーヴィなサウンドを演じ(特に強靭なベース)、とても躍動感のある1曲です。透明感のあるジョニーのギターも相まって、明るくて爽やかな印象の良曲です。「Miserable Lie」は序盤の低いテンションから、途中で加速してロック色の強い攻撃的な演奏へと変貌しますが、モリッシーのボーカルはあまりノっていない気がします。そして後半遅れてノってきたかと思えば、ファルセットで延々歌い続けるという、なんというかズレていて変な感じ。笑 でも良くも悪くもこれが妙に耳に残ります。「Pretty Girls Make Graves」はリズミカルな演奏ではあるものの、曇天のような哀愁が立ち込めています。アウトロの繊細で切ないギターが良い。「The Hand That Rocks The Cradle」はテンション低めなモリッシーの歌と地味なメロディのせいで埋もれがちですが、繊細なギターにグルーヴ感のあるベース、力強いドラムと、スミスの演奏陣の特徴が表れています。そして名シングル「This Charming Man」。米国盤やCDでは6曲目に位置するものの、実はオリジナルの英国盤LPには収録されなかったようです。僅か3分にも満たない短い曲ですが、本作では出色の出来となる名曲です。イントロから躍動感あるノリノリな演奏で惹きつけ、モリッシーのなよなよしたボーカルがキャッチーなメロディを歌います。そしてPVでは花束をぶんぶん振り回すモリッシー、これも結構インパクトがあります。笑
レコードB面のオープニングを飾る「Still Ill」は次作にも通じる演奏で、躍動感あるリズム隊に絡むジョニーのアコギが爽やかで美しいです。伸びやかに歌うモリッシーの歌ともうまくマッチしていて聴き心地が良いですね。「Hand In Glove」はシリアスな空気を纏っています。メランコリックなギターとは対照的に力強いドラムが際立ち、そのせいか比較的ハードな印象を受ける1曲です。続く「What Difference Does It Make?」は小気味良い演奏に踊り出したくなりますが、メランコリックな歌によって内省的で暗い印象が強いです。「I Don’t Owe You Anything」はメロディアスなボーカルをゆったりと聴かせます。演奏は全体的に単調ですが、時折ドリーミーな音色で優しさを見せます。最後の「Suffer Little Children」も楽曲は単調で、歌も鬱々としていて盛り上がりません。でもジョニーの優しく繊細なギターに浸ることができます。
楽曲の出来にはばらつきはあるものの、全編を通して繊細で美しいギターが聴けます。でもそれが必ずしも癒しとならないのは、モリッシーの独特の歌唱もあるかもしれません。アンマッチ感もありますが、不思議と惹きつけます。
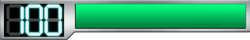
1985年 2ndアルバム
ジャケット写真は反戦映画『In The Year Of The Pig』からの引用で、オリジナルは『Make War Not Love』と書かれいたヘルメットの文字を『Meat Is Murder (食肉は殺人だ)』と書き換えています。これは菜食主義者であるモリッシーからの強烈なメッセージをタイトルに据えた本作は、攻撃的なタイトルに比例してかスミスの全作品で最もロックの躍動感を感じられる1枚に仕上がっています。小気味よいギターに、リズム隊も加えて爽やかなサウンドを奏でていますが、そこに陰を落とすのは脱力感のあるモリッシーの歌唱によるところも大きいかと思います。ヘロヘロで、およそロックに似つかわしくないボーカルですが、この不思議な化学反応が意外とクセになるんですよね。
サッチャー政権下で不況や貧困に喘ぐ若者の声を代弁した存在として、スミスは英国の若者に絶大な人気を誇りました。また英国ではメインストリームがニューロマンティック勢をはじめニューウェイヴ全盛期でしたが、スミスは正統派ロックを奏でる数少ない存在としても輝いていました。本作はオリジナルアルバム唯一の全英1位獲得作品です。
イントロから強い求心力のある「The Headmaster Ritual」で一気に引き込まれます。この魅力的なオープニング曲のおかげで再生頻度も多いです。笑 なよなよしたモリッシーの歌声がメランコリックなメロディを歌い、それを引き立てるアコギとエレキを絡めた爽やかな音色と、グルーヴィなベースと力強いドラムのおかげで躍動感もあります。ですが楽曲の持つ爽快な印象とは裏腹に、教師が校内で暴力を振るう現状を批判した攻撃的なメッセージが込められています。続く「Rusholme Ruffians」ではカントリーを取り入れたような楽曲で、ジョニー・マーの小気味良いギターにアンディ・ルークのブイブイ鳴るベースが特に印象的。跳ねるようなノリの良さがあります。「I Want The One I Can’t Have」は冒頭で閉塞感のある音響効果を突き破って、爽やかな楽曲が展開されます。テンポも速くてノリノリの軽やかな演奏ですが、モリッシーの歌うメロディはキャッチーながらも憂いに満ちています。「What She Said」、小気味良いエレキギターとマイク・ジョイスの手数の多いドラムが畳み掛けるように緊張感を生み出します。ハードなサウンドに加えて、歌も緊張を高めます。早死を願う彼女を悲しむ歌詞です。ここまで勢いのある楽曲が並びましたが、一転して「That Joke Isn’t Funny Anymore」は静かで穏やか。3拍子のリズムで、アコギをはじめ柔らかいサウンドに乗せてメロディアスな歌を歌います。後半に神秘的なエフェクトが入り、終盤は特に美しい印象です。続いてシリアスな空気が立ち込めるスミスの名曲「How Soon Is Now?」。これはオリジナルの英国盤には無く、米国盤やCD再発時に追加された1曲だそうです。ちなみにロシアのt.A.T.u.にもカバーされています。「It’s gonna happen now (今にやって来るさ)」という慰めに対する「How soon is now? (今にっていつなんだ)」と卑屈なメッセージを放ちます。ピンと緊張の張り詰めた重たい演奏が魅力的な、ダークな1曲です。
そしてレコードB面、前曲の重たい空気を吹き飛ばすアップテンポ曲「Nowhere Fast」。カントリーを軸に、より骨太にしたような躍動感溢れる楽曲を繰り広げます。小気味良いギターに強靭なリズム隊がノリノリな演奏を展開しますが、相変わらず歌はメロディアスで陰りがあります。続いて「Well I Wonder」はジョニーのアコギが繊細な音色を奏で、全体には陰鬱な空気を纏っています。歌は耽美でアンニュイな感じで、後半は裏声に切り替えますが、悲哀な印象を与えます。そして「Barbarism Begins At Home」は耳に残るフレーズを刻むギターと、グルーヴ感溢れるリズム隊がとてもカッコ良い。躍動感がありますが、爽やかさを上回るシリアスな空気が立ち込めます。そして時折奇声を上げるモリッシーのボーカルが少し異質です。ラストは表題曲「Meat Is Murder」。牛の鳴き声から始まるこの楽曲は「食肉は人殺しと同じだ、動物の鳴き声に誰が耳を傾けるのか?」と強いメッセージを放ちます。歌詞を反映したか悲しげな音色を奏でるギター、そしてどうしようもなく陰鬱な雰囲気…暗すぎるラストです。
次作の方が最高傑作に挙げられることが多いですが、最初の1枚として聴くには、取っつきやすさは本作の方が上です。爽やかで大好きな本作。個人的にも次作よりもこちらの方が聴く頻度は高いです。
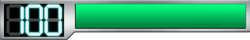
1986年 3rdアルバム
不況に苦しみフラストレーションを溜めた若者たちの心を代弁する存在として、絶大な支持を得ていたスミスは、本作でその矛先をサッチャー政権だけでなく英国王室にも向けました。全英2位のヒットとなった本作はスミスの最高傑作と名高い作品です。2ndとも甲乙つけがたいですが、完成度の高さは本作に軍配が上がります。なおジャケットアートで横たわる写真は俳優のアラン・ドロン。モリッシーが彼のファンなのだそうです。
ジョニー・マーのクリアなギターサウンドに、アンディ・ルークとマイク・ジョイスという強靭なリズム隊。そんな爽やかで躍動感ある演奏とモリッシーの耽美で独特なボーカルは少しギャップがあって、それがまた魅力的なんです。
「The Queen Is Dead (Take Me Back To Dear Old Brighty)」で始まります。タイトルからして強烈。1962年の映画「The L-Shaped Room」からの短い引用が流れたあと、強いエコー処理を施したドラムが始まりを告げます。強烈に唸るベース、そしてガチャガチャかき鳴らすギターも緊張を高め、スリリングな演奏に痺れます。モリッシーの歌声にも力がこもりシリアスな雰囲気。非常にカッコ良い名曲です。続く「Frankly, Mr. Shankly」は躍動感あるリズム隊に小気味良いアコギが絡む演奏で前作のように爽やかですね。そしてリズミカルな演奏に合わせて歌メロの語感がとても良く、なかなか愉快な印象です。しんみりとして静かな1曲「I Know It’s Over」は、ジョニーの繊細なアコギが美しい。モリッシーの歌は諦めのような悲哀に満ちていて、後半に向け徐々に感情がこもって盛り上がりますが、これがとてもドラマチックなんです。切なくも美しい楽曲です。そして前曲の流れを汲みつつ、更に陰鬱な「Never Had No One Ever」。どうしようもない暗さや冷たさが楽曲を支配し、モリッシーの歌は耽美さを保ちつつも悲痛な叫びのようです。そこからアルバムは流れを少し変え、「Cemetry Gates」では暗闇から抜けたような救いがあります。小気味良いアコギや躍動感あるベースが爽やかにネオアコサウンドを奏でますが、でも底抜けに明るいわけではなく、そこには哀愁や切なさが漂います。これも良曲ですね。
そしてアルバム後半の幕開けとなるアップテンポ曲「Bigmouth Strikes Again」。スリリングでカッコ良い1曲です。アコギが小気味良くチャカチャカ鳴り疾走感を与え、ドラムがスコンと気持ち良く抜けます。サビでは、ピッチを変えてヘリウムを吸ったような声のコーラスが妙に耳に残りますが、モリッシーは自分の声にエフェクトを掛けて試すのが好きだったようです。「The Boy With The Thorn In His Side」は爽やかなギターポップを繰り広げます。春の陽射しのような暖かく柔らかい演奏に、明るくも切なさを纏ったメロディアスな歌で癒やしてくれます。そして「Vicar In A Tutu」ではテンポアップ。2分強の短さですが、アルバム後半のアクセントとなるノリの良い楽曲を展開します。カントリーっぽい感じですね。続いて名曲「There Is A Light That Never Goes Out」。アコギの柔らかな音色にグルーヴィなベースが絡みます。サビメロではストリングスも加わり、美しく切ない歌メロを更に引き立てます。そして歌詞では「もし二階建てバスが突っ込んできても、君のそばで死ねるならなんて最高の死に方だろう」と、悲劇的ですがモリッシー流の美学が表れています。ラスト曲は「Some Girls Are Bigger Than Others」。暗鬱ですがリズミカルでノリの良い演奏に、淡々と「ある女の子らは他の女の子らより大きい」とひたすら歌っています。諸説あるものの、「Big」は「豊満」という意味で歌われている説が濃厚なようです。
デラックス・エディションのDisc2はレア音源集『Additional recordings』、Disc4はDVDで、それぞれレビューは割愛します。Disc3は『Live In Boston』と銘打たれたスミスの貴重なライブ音源で、こちらだけレビューしたいと思います。
ライブは名曲「How Soon Is Now?」で幕開け。あまりにグワングワンと歪んだ音は、ダークさよりもサイケ色が強い印象で、酔いそうな感覚を生みます。ドラムにも強い残響がありますが、ミックスが悪いのかモリッシーの歌だけが空間に響いていない感じで、若干違和感があります。でもスリリングな演奏の魅力が上回りますね。続く「Hand In Glove」はジョニーがメランコリックなメロディを奏でますが、躍動感あるリズム隊のおかげでノリが良いですね。歌メロも耳に残ります。歓声が上がると、続いて「I Want The One I Can’t Have」へ。アンディの強靭なベースに、マイクの畳み掛けるようなドラムで躍動感たっぷり。キャッチーで明るい歌メロに加えて、テンポの速さも相まって爽快な印象です。後半モリッシーの歌はこぶしが効いていたり、変なファルセットをかましたりと表情豊かです。そして「Never Had No One Ever」で一気にどん底へ。救いのない暗さがあります。作り込まれたスタジオ盤とは違って多少の粗さがありますが、重低音が効いていて迫力があります。また、アウトロのギターソロも哀愁たっぷりで渋いですね。「Stretch Out And Wait」は3拍子のゆったりとしたリズムに乗せて、優しい楽曲を繰り広げます。続く「The Boy With The Thorn In His Side」は晴れやかで暖かく、ドリーミーな音色とメロディアスな歌で癒やしてくれます。残響が美しさをより引き立てて魅力的な仕上がりです。「Cemetry Gates」はエフェクトをかけたギターによって澄んだ水の中にいるような感覚があり、小気味良く刻むドラムによって躍動感を合わせ持ちます。スタジオ録音とは違った印象ですが、これはこれで魅力的なアレンジです。メドレー形式の「Rubber Ring / What She Said / Rubber Ring」は、マイクのリズミカルなドラムをはじめ即興的な雰囲気の演奏から、緊張感溢れる「What She Said」へ雪崩込みます。ダイナミックなドラムにスリリングなギターがカッコ良い。「Is It Really So Strange?」はリズミカルなドラムのおかげでノリが良く、比較的明るい印象です。そして名曲「There Is A Light That Never Goes Out」。若干テンポを落としているのかスタジオ版よりもゆったりとした印象で、また原曲の悲劇的な美しさとは違って比較的リラックスしたムードが漂います。続く「That Joke Isn’t Funny Anymore」はメロウなギターが優しい音色を奏でます。最初はゆったりとしていて癒やされますが、後半に向かうにつれどんどん盛り上がってドラマチックな印象に。そして非常にひりついている「The Queen Is Dead」。太鼓のようなダイナミックなドラムが全体を鼓舞し、そして切れ味抜群のギターや攻撃的なモリッシーの歌によって、スタジオ版を大きく上回る恐ろしい緊張感を放ちます。カミソリのような切れ味でとてもスリリングです。ラストは一転して落ち着いた「I Know It’s Over」。前曲のハイテンションが嘘のように、ダウナーで憂いたっぷり。そして哀愁に満ちているものの美しいんです。
ネオアコ基調ですが、爽やかな楽曲についても哀愁や寂寥感を振り払いきれておらず、アルバム全体には暗鬱な空気が漂っています。疾走感と緊張感のある「The Queen Is Dead (Take Me Back To Dear Old Brighty)」や、あまりに美しい「There Is A Light That Never Goes Out」をはじめ、名曲揃いの名盤です。
左:ジャケットが一新されたデラックス・エディション。
右:通常ジャケット。
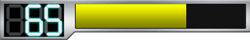
1987年 4thアルバム
モリッシーとジョニー・マーの関係性悪化が原因で、本作のリリースを待たずしてスミスは解散を宣言。結果的に本作はラストアルバムとなりました。これまでほぼ全ての作曲をジョニーが、作詞はモリッシーが担当しており、今作でもそれは変わらずなのですが、2人の関係性の悪化が影響してかこれまでの3作品からの変化を感じます。繊細なアコースティックギターからエレキギター主体になった曲もいくつか見られ、シンセの活用が進んで曲作りもやや豪華になった感があります。
「A Rush And A Push And The Land Is Ours」で始まります。メランコリックで冷たい雰囲気ですが、途中から加わるリズミカルでグルーヴィなリズム隊によって躍動感が追加されます。モリッシーが野太く唸る部分が良くも悪くも印象に残ります。「I Started Something I Couldn’t Finish」ではソリッドなエレキギターが鳴り、ジョニーの繊細な演奏をするイメージが変わってしまった印象。加えてビート感の強いドラムやホーンの音色など一聴すると彼ららしくない感じがして、初めて聴いたときには軽い拒否反応を覚えました。でも楽曲はモリッシーのオールディーズ趣味が表れているし、憂いのある雰囲気は踏襲しています。続いて「Death Of A Disco Dancer」。静かな空間にアンディ・ルークのベースとモリッシーの歌が鬱々としたダウナーな雰囲気を作り出し、ノイズのような音を立てるギターが不穏な感じ。哀愁の歌に浸っていると、終盤にはダークで神経質な演奏によって闇に呑み込まれるような感覚に陥ります。そして「Girlfriend In A Coma」は、繊細なアコギと躍動感のあるリズム隊が、爽やかで温かみのあるアコースティックサウンドを奏でます。僅か2分の小曲ですがこれまでのスミスらしさを感じられる1曲で、救いのような優しさに溢れています。「Stop Me If You Think You’ve Heard This One Before」はマイク・ジョイスの力強いドラムをはじめ、イントロで高揚感を煽ります。躍動感と繊細さを両立させた楽曲づくりは踏襲しつつ、モリッシーの歌唱法が変わったのかこれまでと違う印象も受けます。
アルバム後半のオープニング曲は絶望的に暗い「Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me」。大衆の嘆きのような叫び声をバックに、冷たいピアノが暗いムードを演出する冷たい2分間。その後に歌が始まりますが、ダークさを引き立てて絶望が漂います。シンセストリングスを用いたサウンドは、スミスにしてはやや過剰演出にも思いますが、どん底を突きつけるインパクトがあります。一転して「Unhappy Birthday」はシンプルなネオアコサウンドで、リズミカルで爽やかさがあり、アンニュイな歌が魅力的です。とは言えタイトルにもあるように歌詞は明るい内容ではなく、自分を捨てた相手に対してわざわざ「誕生日ご愁傷さま」と悪意をぶつける内容だったりします。続く「Paint A Vulgar Picture」も憂いを帯びつつ晴れやかさも両立した楽曲で、牧歌的な優しさがあります。初期スミスのように、派手さはないものの良質なメロディに魅せられます。「Death At One’s Elbow」は2分程度の短い楽曲で、カントリーを発展させたような、小気味良くて妙にコミカルな雰囲気が出ています。そしてラスト曲は「I Won’t Share You」。ドラムレスのシンプルな楽曲で、繊細で心地良いアコギやモリッシーのアンニュイなボーカルが優しく語りかけます。
初めて聴いたときには、2ndや3rdに比べて若干過剰演出気味に聴こえて馴染めませんでした。ですが改めて聴くと地味ながらも良質な楽曲に、意外と良いなという感想に。ちなみにメンバー4人それぞれお気に入りとして本作を挙げているのだそうです。
1987年、スミスは僅か5年の活動期間を終えることになりますが、ロック界や英国の若者に多大な影響を与えました。
編集盤
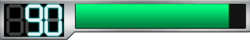
1984年
BBCの音楽番組向けに収録したスタジオライブ音源や、アルバム未収録シングルを中心としたコンピレーション盤です。メンバーは1st『ザ・スミス』の制作に不満があったらしく、また件の作品は巷での評価もパッとしないため、コンピレーション盤である本作の方が実質的な1stアルバムと見做されることもあります。
アルバムは「William, It Was Really Nothing」で幕開け。ジョニー・マーの透明感のあるギターやモリッシーのご機嫌な歌など、爽やかで軽やかな印象でオープニングにピッタリなこの楽曲はアルバム未収録シングルです。続く「What Difference Does It Make?」はマイク・ジョイスの力強いドラムをはじめ躍動感溢れるリズム隊が際立ちます。リズミカルで跳ねるようにノリノリな演奏ですが、歌には影があって哀愁があります。続く「These Things Take Time」はアンディ・ルークの強靭なベースがインパクトのある、ロック的な躍動感に溢れる爽快な楽曲です。骨太なリズム隊と繊細なギター、なよなよボーカルというスミスの特徴がよく表れていますね。爽やかでカッコ良いです。続いて代表曲「This Charming Man」。小気味良くてノリの良い爽やかな演奏ですが、終盤はやけにマッチョなベースが際立っていてカッコ良い。またキャッチーな歌メロも気持ち良いですが、貧しい少年が魅力的な男性に出会って援助を受けていくという同性愛的な内容が歌われています。そして名曲「How Soon Is Now?」。2ndアルバム『ミート・イズ・マーダー』の再発盤にも収録されています。ダークな空気を醸し出すエフェクトがかった幻覚的なギターが魅力的で、メランコリックな歌と合わせて切ない気分に浸ることができます。そして幻覚的なギターとは対照的にドラムの輪郭はクッキリしていて力強い印象。電子パーカッションも使われているようですが、間奏でキンコン鳴っている楽器でしょうか?「Handsome Devil」はリズム隊が力強くて激しい楽曲です。ハードな仕上がりですが、リズミカルでノリノリです。「Hand In Glove」はフェードイン処理がされています。グルーヴ感や躍動感のある演奏ですが、全体的にはシリアスな雰囲気で緊張が張り詰めています。続いて、イントロとアウトロでハーモニカを鳴らすアレンジが加わった「Still Ill」。速いテンポで刻むタイトなドラムに細かいギターが特徴的で、『ザ・スミス』版よりもリズム隊が強調されていますが、なんとなくこじんまりとした印象を受けます。
ここからアルバム後半戦。「Heaven Knows I’m Miserable Now」は毒気のないリラックスした演奏に乗せて、モリッシーの伸びやかな歌を聴かせます。「This Night Has Opened My Eyes」は落ち着いた演奏ですが、前曲とは一転して暗く憂いを帯びています。オールディーズっぽいレトロな雰囲気はモリッシーの趣味でしょうか。「You’ve Got Everything Now」は力強いベースを軸に、今にも弾け出しそうなパワフルな演奏を繰り広げます。ですがどこか鬱屈としてフラストレーションを溜めているような印象をも受けます。続く「Accept Yourself」は骨太で力強いリズム隊、特にマイクのパワフルなドラムに対して、アコギの小気味良い音が爽快。バックのノリの良い演奏に思わず聴き入ってしまいます。カッコ良い。「Girl Afraid」はジョニーのギターにサーフロック的なノリの良さを感じつつ、曇天のような暗鬱な空気が払拭しきれていません。「Back To The Old House」は優しく美しいアコギの調べに思わず聴き入ってしまいます。モリッシーの囁くような歌もありますが、ジョニーのアコギが主役の1曲です。「Reel Around The Fountain」はドラムが単調な割にやけに音量が大きく悪目立ちしていますが、メロディアスなモリッシーの歌の方が聴きどころです。最後の「Please Please Please Let Me Get What I Want」は2分足らずの小曲ですが、これが美しい。アコギやマンドリンを鳴らして牧歌的で神秘的でもある優しい演奏と、アンニュイなモリッシーの歌に癒やされます。
大半を占めるスタジオライブ録音が影響してか、元々強靭なリズム隊が更に際立っていて、躍動感に溢れています。全16曲とボリューミーですが1曲1曲がコンパクトなので、トータル56分と長すぎず丁度良いですね。
ライブ盤

1988年
『ザ・クイーン・イズ・デッド』に伴うツアー模様を収めた、スミス唯一のライブ盤となります。ちなみに1986年の初頭にアンディ・ルークがヘロイン中毒で解雇され、代役としてクレイグ・ギャノンをベーシストに迎えますが、僅か2週間で復帰を許されたアンディが戻ってくるという出来事がありました。クレイグはリズムギターに転向して半年ほどバンドに在籍、同年10月に脱退しますが、本作ではその5名体制時スミスによるライブを聴くことができます。
モリッシーの「Hello」の挨拶で始まりますが、なよなよしたスタジオ録音の印象とは程遠い、力強いだみ声で驚かせます。その直後に「The Queen Is Dead」でライブは幕を開けます。マイク・ジョイスのアグレッシブなドラムをはじめ、緊迫感のあるスリリングな演奏がカッコ良い。歌も時折巻き舌気味だったり攻撃的な印象です。続く「Panic」はリズミカルなドラムがノリノリで高揚感を煽り、牧歌的で少し哀愁のある歌メロも優しくて心地良いですね。「Vicar In A Tutu」はバタバタと忙しないドラムにゴリゴリと硬質なベースが下支え。そこにウェスタンっぽいギターが絡んで躍動感を与えてくれます。スタジオ版よりも若干リズム隊がパワフルな印象。「Ask」は、モリッシーの吐き捨てるようなタイトルコールの後に、爽やかで小気味良い楽曲が展開されます。テンポも速くて軽快ですね。続いてメドレーの「His Latest Flame/Rusholme Ruffians」は軽やかなギターとグルーヴ感抜群のベースに始まり、ドラムも遅れて加わってノリノリの演奏を繰り広げます。自然と踊り出したくなるような躍動感に満ち溢れています。ノリノリの楽曲が続きましたが、「The Boy With The Thorn In His Side」ではジョニー・マーのギターが哀愁を誘います。爽やかだけどメロディアスで切ないですね。美しい楽曲です。「Rubber Ring/What She Said」のメドレーはブルージーでリズミカルな演奏に始まり、モリッシーのだみ声を皮切りに、なだれ込むような演奏でテンションを高めます。マイクの激しいドラムが特にカッコ良い。「Is It Really So Strange?」は力強いイントロから、リズミカルかつ少しレトロな雰囲気が漂う歌メロパートへ。ポップで楽しいです。続いて名曲「Cemetry Gates」。切なさを纏いつつも爽やかな楽曲で、メロディアスな歌に加えて、力強いベースに柔らかなギターが心地良さを提供。アウトロでギターをミスったのか一瞬止まりますが、全体的には良好です。そして「London」はパワフルかつヘヴィで、パンキッシュな1曲です。緊迫感のあるひりついた演奏ですが、時折開放感を出して緩急つけています。ラストはテンポアップして非常に激しい演奏を聴かせます。8分近くある「I Know It’s Over」は、前曲の激しさが嘘のように、諦めのような穏やかさと哀愁が漂います。メロディアスな歌と演奏に浸っていると、徐々に激しさが増してじわじわと盛り上がっていきます。聴いているとこみ上げてくるものがありますね。「The Draize Train」は、メタリックで強靭なベースと2人のギターを軸に、シリアスで緊張感のある演奏を繰り広げるインストゥルメンタル。スリリングで中々カッコ良いです。「Still Ill」はカチャカチャと無機質なロボットのようなイントロで始まり、そこから爽やかな演奏に切り替えて歌メロへ。時折だみ声や巻き舌を混ぜたモリッシーの歌も絶好調ですね。最後は疾走感のある「Bigmouth Strikes Again」。陰のある雰囲気を纏いつつ小気味良さもあるスリリングな演奏は踏襲。ですがスタジオ版と違ってピッチを上げた変なコーラスがないので、こちらの方が聴きやすいかもしれませんね。変なコーラスはないものの、疲れもあるのか時折絞り出すような歌唱が特徴的です。
ライブ終了後は観客からの熱い歓声と、アンコールを求める手拍子で臨場感があります。
アップテンポ曲はスタジオ録音よりも激しさが増し、パンクバンドとしての側面が垣間見えます。もちろんメロディアスに聴かせる楽曲の美しさも健在。良質なライブ盤です。
類似アーティストの開拓はこちらからどうぞ。
















