🇬🇧 Bauhaus (バウハウス)
レビュー作品数: 7
スタジオ盤
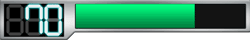
1980年 1stアルバム
バウハウスはイングランド出身のポストパンクバンドです。ピーター・マーフィー(Vo)、ダニエル・アッシュ(Gt/Sax)、デヴィッド・J(B) (フルネームはデヴィッド・ジョン・ハスキンス)とケヴィン・ハスキンス(Dr)のハスキンス兄弟、この4人で1978年に結成しました。当初「バウハウス1919」というバンド名でしたが、1年足らずで現在の「バウハウス」に改名。『魔人ドラキュラ』の俳優を務めた故人ベラ・ルゴシを題材にしたシングル「Bela Lugosi’s Dead」でデビューを果たし、ゴシックロックを打ち立てたバウハウスは「ゴスの帝王」とも呼ばれています。インディーレーベルの4ADよりリリースされた、セルフプロデュースとなる本作はゴシックロックの名盤として名高いです。
1988年のCD化に際してシングル「Dark Entries」を1曲目に据える変更がされていますが、私の持っているバージョンはオリジナルどおり「Double Dare」で幕を開けます。「Dark Entries」はダウナーかつスリリングな疾走曲なので、これで始まるバージョンの方が良さそうですね。
さて、オリジナルバージョンのオープニング曲「Double Dare」ですが、非常にノイジーで歪んでいます。脳を浸食しそうな幻覚的で不快な音と、地を這うような重低音が不穏な気配を作り出します。テンポは遅いのですがとてもヘヴィで、楽曲が進むにつれてどんどん攻撃的になっていきます。ピーターの歌もシャウト気味。続く「In The Flat Field」は焦燥感を煽る疾走曲。言うほど速くはないですが、躍動感のあるドラムが気分を高揚させ、そして奇怪なギターとボーカル、淡々としたベースが恐ろしく不安を掻き立てます。バウハウスはデヴィッド・ボウイやT・レックスをカバーしているんですが、ピーターのボーカルスタイルはこれらグラムロックアーティストの影響を大いに受けていますね。「A God In An Alcove」はギャング・オブ・フォーにも通じる切れ味抜群のカミソリギターが強烈。攻撃的ですが陰のある楽曲です。続いて「Dive」はダニエルのカッコ良いギターリフとケヴィンの高速ドラムが爽快な疾走感を作り出します。ボンボン唸るベースも結構カッコ良い。ですがサックスや無機質なSEがそれを不気味な空気に変えてしまいます。僅か2分程度の短い楽曲ですが、スリリングで魅力的です。「Spy In The Cab」は哀愁漂う楽曲。グラムロック風の独特の歌唱でメロディアスな歌を歌いますが、音数の少なさに加えてピュンピュン鳴る無機質なシーケンサーによって、暗くて不気味な印象に仕上がっています。終盤ではギターが不快なほどノイジーな音を奏でているし…。
アルバム後半は「Small Talk Stinks」で開幕。リズミカルでノリも良く、楽しげな音を奏でようとしている感じはします。歌も前半の楽曲に比べれば若干明るめというか、ひねくれポップな感じ。ですが歪んでヘヴィなギターがこの楽曲で浮いていて、奇怪さが際立っています。そういうチグハグな感じを狙っているんでしょうか。「St. Vitus Dance」は躍動感のあるドラムがカッコ良い。ですが狂気じみたボーカルと、ラリったような奇怪なノイズ(ギター音?)が終始飛び交っていて、一筋縄ではいきません。気持ち悪いのに、不思議と中毒性もあります。「Stigmata Martyr」は這うようなベースとノイジーなギターが焦燥感を煽ります。ダーティで怪しげなサウンドはゾクゾクするほどカッコ良い。ラスト曲は7分に渡る「Nerves」。歪んだ音やノイジーなSEにより実験的な演奏を展開した後、2分頃から引きずるように重たいギターリフが、おどろおどろしいフレーズを奏でます。不気味な静寂の中で淡々と進む歌は感情が高ぶると怒鳴るかのようでスリリングだし、時折現れる狂気的なピアノやおどろおどろしいギターリフなど、怪しげで独特のサウンドは良くも悪くも耳に残ります。
全体的にはヘヴィで攻撃的、そして不気味な印象を抱きます。そして主にダニエルのギターだと思いますが、聴いたこともないような奇怪でノイジーなサウンドが飛び交います。
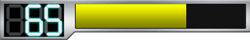
1981年 2ndアルバム
レーベルを4ADからベガーズ・バンケットに移してリリースされたバウハウスの2ndアルバムです。キーボードを導入したり、ファンクのリズムを取り入れてダンス要素を出したりするなど幅を広げ、相変わらず奇怪ではあるものの前作よりは若干トゲが少なくなった印象を受けます。ジャケットアートはギタリストのダニエル・アッシュによるもの。
「Hair Of The Dog」はダニエルの奇怪なギターサウンドで始まり、そこからケヴィン・ハスキンスのダイナミックなドラムで引き込みます。同じフレーズを反復してダークで怪しい世界観を展開しますが、時折入る耳をつんざくような絶叫にはビビります。「The Passion Of Lovers」はデヴィッド・Jのベースとケヴィンのドラムが力強いリズムを刻み、そして繊細なアコギのやひんやりとしたシンセが入るなど聴きやすくなりました。何よりピーター・マーフィーの歌うメロディがメロディアスで、セオリーを無視して何をやってくるかわからない前作からは格段の進歩だと思います(メロディ重視なのはこの楽曲くらいですが)。続く「Of Lillies And Remains」は無機質な時計のようにギターが変な音を一定のリズムで刻み、リズム隊がサポート。淡々として無機質な演奏に乗るのはナレーションのような語りで、後半少しメロディが出てくる感じ。奇怪で不気味な楽曲です。「Dancing」は怪しげでリズミカルな楽曲。マッチョなベースに歪んだギター、怒鳴るようにテンションの高いボーカルなど焦燥感を煽り立てます。ドラムはタッタカタッタカ爽快なんですけどね。「Hollow Hills」はひんやりとしたシンセと、低音でメロディを刻むベースが不気味な静けさを作り出します。大きな盛り上がりもなく、幽霊でも出てきそうな怪しげな雰囲気が終始続きます。
アルバム後半は「Kick In The Eye」で幕開け。ファンキーで、ディスコ音楽もかじったダンサブルな楽曲です。ノリが良いのですが明るいわけではなく、ダークさというか怪しげな雰囲気が払拭できていません。そんなアンバランスさが不思議と耳に残ります。続いて、ピーターのテンション高いコールで始まる「In Fear Of Fear」。リズミカルなビートは爽快なのですが、ダニエルのサックスがギターのカッティングのように短く刻む独特の吹き方をしており、そこにスペイシーのSEが絡むものだから妙な気持ち悪さがあります。「Muscle In Plastic」はバタバタとしたケヴィンのドラムがカッコ良く、デヴィッドのベースと絡んで気持ちの良いグルーヴを生み出しています。そこにキンキンとしたギターや吐き捨てるようなボーカルスタイルが乗っかると、妙に焦燥感を煽られるんですよね。終盤のピアノも狂気的な印象です。「The Man With The X-Ray Eyes」は力強いドラムやリズムギターが気持ちの良いビートを刻み、ベースが低音でメロディを奏でます。演奏が爽快で、結構やみつきになるんですよね。最後に表題曲「Mask」。ノイズが響き渡り、エコーの効いたピーターの歌などおどろおどろしく怪しげな雰囲気が漂います。中盤から現れるエキゾチックな音色が、不気味な美しさを描きます。
尖りまくった前作に比べると、本作も攻撃的ではありながら、ダンスビートが効いていたりメロディの美しさが出始めるなど少し聴きやすくなりました。

1982年 3rdアルバム
取っつきにくさのあるバウハウスですが、本作は1stや2ndにある攻撃性を帯びつつも、聴きやすい楽曲が多い傑作です。ジャケットアートに関しては不気味で一番取っつきにくそうなんですけどね。笑 メロディアスで繊細な一面も垣間見え、耽美で陰鬱な世界を楽しめる一方、バウハウスの特徴でもあった攻撃的な楽曲も健在で、それらは奇怪さが薄れて聴きやすくなりました。純粋にカッコ良いです。
アルバムのオープニングを飾る「Third Uncle」は巨匠ブライアン・イーノのカバー曲。デヴィッド・Jによるノリノリのベースソロから、キレッキレで躍動感のある演奏が繰り広げられます。演奏は強い緊張を帯びつつも、ひたすら反復するリズミカルなフレーズは高揚感を煽ってきます。そして楽曲が進むにつれて、ピーター・マーフィーの淡々とした歌はテンションがどんどん高まり感情的になっていきます。1曲目から一気にアルバムに引き込んでくる、病み気味ですがスリリングでカッコ良い楽曲です。続く「Silent Hedges」は暗鬱で哀愁漂うメロディアスな楽曲。ダニエル・アッシュのギターはこれまでのスタイルと異なって繊細な側面を見せてくれます。そして徐々に高ぶってくると、ダークでスリリングな楽曲へと様変わりします。「In The Night」は武骨なリズムと荒いギターが淡々と進行。ですが途中からテンポアップして、とてもスリリングな楽曲に。狂気じみたピーターの歌も印象的ですね。「Swing The Heartache」は数十秒ほどの静寂を経て、無機質でメタリックな演奏が始まります。特に銃声のように鋭いケヴィン・ハスキンスのドラムが強烈ですね。演奏は人を寄せ付けない感じなのですが、意外にも歌はしっかりしたメロディを力強く聴かせ、応援歌のような雰囲気でキャッチーさすらあります。「Spirit」はダイナミックなドラムと繊細なギターが対照的。少しエキゾチックな香りも漂いますがメロディはキャッチーで、中盤まではバウハウスの攻撃性やダークさが少なく聴きやすいです。でも終盤盛り上がるにつれてカオスで狂気的な顔を見せるという…。
アルバム後半は組曲を展開。「The Three Shadows, Part I」は静かに聴かせるインストゥルメンタル。ダニエルの陰鬱なギターを中心に、時折神秘的な音が加わってきます。暗さの中にエキゾチックな雰囲気もありますね。「The Three Shadows, Part II」に入ると静かで暗鬱な演奏は8分の6拍子のリズムで揺さぶってきます。ピーターは哀愁ある歌をじっくりと聴かせ、暗く内省的なのですがどこか心地良さを感じられる楽曲に仕上がっています。組曲ラストの「The Three Shadows, Part III」は前2パートとは異なり、無理矢理テンションを上げようとして無機質さが際立つ、奇怪な印象。「All We Ever Wanted Was Everything」はアコギとベース中心のシンプルな演奏に、ピーターがしっとり聴かせます。耽美で歌心のある歌や繊細な演奏で、1stでは考えられないくらい彼らの成長を感じます。最後の「Exquisite Corpse」はいくつかの短い楽曲が現れては消える、実験的で理解しがたい楽曲です。ダニエルとデヴィッドが一部パートでボーカル参加。序盤はダブを取り入れて不可思議な展開、そして中盤からは心が洗われるかのような美しいピアノに癒されます。しかし咳払いとともに楽曲にダークな雰囲気が立ち込めます。悲壮感のある叫びが響いたかと思えば、場違いなレゲエが始まります。その後また場面転換し、アルバムタイトルである「The Sky’s Gone Out」を連呼しながら、美しいピアノとレゲエのリズムというチグハグでカオスな展開。そして唐突に終わったかと思えば語りが入るという…。
攻撃的な演奏もあるのですが、内省的な楽曲や静寂を感じさせる楽曲が増え、アルバム全体に深みが出てきました。それでいて尖りまくった部分が削ぎ落とされ、程良く鋭利でちょうど良い聴きやすさです。入門に向いていると思います。
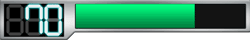
1983年 4thアルバム
本作は現役時代のラストアルバムです(後に再結成して作品を出したため最終作では無くなりました)。前作からメンバー間の対立が表面化していましたが、本作のレコーディング中にピーター・マーフィーが2週間ほど入院して参加できなかったとき、残りの3人はとてもリラックスして曲作りが出来たというエピソードも。そんな経緯から、本作にはダニエル・アッシュやデヴィッド・Jがピーターの代わりにボーカルを取る楽曲も入っています。ピーターはレコーディングの延期を求めましたが聞き入れられず、そのままリリースを決行。メンバーの亀裂も決定的になり、アルバムリリース前にバウハウスは解散しました。
開幕「She’s In Parties」は退廃的でメランコリックな名曲です。ダニエルのノイジーなギターはどこか哀愁が漂い、ピーターの歌も憂いを帯びているため、聴いていると感傷的な気分になります。この切なさがたまりません。暗く暗く沈んでいく感覚に加えて、終盤では音数を減らし残響音が強調された不気味な演出でジョイ・ディヴィジョンっぽさも感じます。続く「Antonin Artaud」はダニエルのギターが緊迫した空気を作り、野太いコールに変な歌が始まります。ケヴィン・ハスキンスの刻むリズミカルなドラムが、このひねくれた楽曲を妙に盛り上げています。メロディがコロコロ変わり、終盤は怒鳴り声が重なり合って非常にカオスな状態に。僅か20秒のインスト曲「Wasp」を緩衝材として挟むと、続く「King Volcano」ではトラッドのような美しくも哀愁を帯びたアコギの音色に癒されます。楽曲が進むと合唱が始まりますが、呪術的…というほどでは無いにせよ、どこか怪しげな空気に変わります。「Who Killed Mr. Moonlight?」ではケヴィンのエレピがシンプルで美しい音色を奏で、ポツポツと呟くようなピーターの歌が乗ります。音数の少なさゆえに寂寥感に満ちた印象。時折テンポアップして盛り上げては、また静寂が訪れて寂しさを呼び戻します。少しアンビエントっぽいですね。
アルバム後半は「Slice Of Life」で幕開け。憂いを帯びたアコギが美しい音色を奏でます。囁くように歌っているのはピーターの代わりにボーカルを取るダニエル。楽曲は暗く沈んでいくような物悲しい雰囲気です。続く「Honeymoon Croon」はガヤガヤとノイジーなギターに力強いリズムで前曲とは雰囲気が変わりますね。「Kingdom’s Coming」は再び繊細なアコギ主体で、寂寥感が漂います。アクセントとして加わるピアノも神秘的ですね。そして表題曲「Burning From The Inside」は9分半に渡る大作です。金属質なギターが奏でるヘヴィでダークなサウンド。途中からリズム隊が加わりますが、これがとてもファンキー。メタルとファンクな演奏を交互に繰り返していきます。そしてピーターの鬱々としたボーカルはデヴィッド・ボウイにも似ています。ラスト曲は「Hope」。毒気が抜けて透明感のある晴れやかな演奏に、コーラスを重ねて歌う賛美歌のような雰囲気。ピーターの関与が少ないと毒気というか攻撃性が薄れるんでしょうか。
全体的にアコースティックな割合が増えて美しくも寂寥感が漂いますが、アルバム通しだとやや散漫な印象。そんな中で名曲「She’s In Parties」が光ります。表題曲もカッコ良いですね。
そしてバウハウスは本作を最後に解散。ピーターは元ジャパンのミック・カーンと組んでダリズ・カーを結成、その後解消してソロキャリアを進みます。ピーターを除く3人はラヴ・アンド・ロケッツを結成。バウハウスの再結成はしばらく経ってからになります。
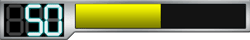
2008年 5thアルバム
1983年に解散したバウハウス。1998年に再結成してツアーを敢行したあと、次の再結成は2005年。ピーター・マーフィー(Vo)、ダニエル・アッシュ(Gt)、デヴィッド・J(B)、ケヴィン・ハスキンス(Dr)のオリジナルメンバーで変わらず、このラインナップで本作が制作されました。邦題のセンスが1970年代っぽいですね。
本作制作時にはまたメンバー間の亀裂が入ってしまい、これがラストアルバムであることとバンドの解散が告げられ、本作のプロモーションツアーも無く活動を休止しました。…といいつつ2019年にまた再結成してるんですけどね。
ノイジーなギターで幕を開ける「Too Much 21st Century」でアルバムが始まります。一定のリズムを刻むベースやドラムには当時の鋭利さやスリルはなく、1970年代頃のまったり心地良いロックといった趣です。ピーターの歌は力強いですが、それも円熟味を帯びてやや落ち着いた印象。「Adrenalin」はゴリゴリとノイジーでヘヴィな音が支配します。普通にカッコ良いのですが、でも当時の狂気性やナイフのような切れ味は無くなってしまい、心地良さすら感じてしまうという。「Undone」はグルーヴ感抜群の楽曲で、特にデヴィッドのベースが気持ち良く響きます。シンセのハーモニーも幻覚的で心地良いですね。終始耽美な歌唱ですが、楽曲がゆったりとしているので気だるげな印象も抱きます。「International Bulletproof Talent」は金属質なギターリフが楽曲を牽引。同じフレーズを反復しますが、これが意外とクセになります。そして低音を活かしたダンディな歌唱はデヴィッド・ボウイにも似ていて好印象です。「Endless Summer Of The Damned」はハスキンス兄弟のリズム隊が当時のポストパンクを彷彿とさせます。切れ味は少し衰えてしまいましたが攻撃性は健在で、バウハウスの全盛期にも通じるスリルがここで聴けます。「Saved」はピーターのアカペラに近い楽曲です。祝詞を奏上するかのような歌い方に、時折静かにドラムやサックスが鳴り響く厳かな雰囲気。後半はバンド演奏が少し前に出てきて、歌もやや狂気性を帯びてきます。「Mirror Remains」は気だるげな演奏で、歌は渋いですね。そんな中ギターだけは警告音のような緊張感ある音を奏でてスリルを掻き立てます。終盤は狂気的なピアノがギターに絡んでカッコ良い。続く「Black Stone Heart」は耽美で色気のあるピーターのボーカルが印象的。演奏は重低音が効いていますが、比較的ノリが良いためそこまで重たさは感じません。そして、7分近い「The Dog’s A Vapour」。スローテンポのダークで神秘的な楽曲で、エコーがかった歌は厳かでスケール感があります。後半は一気に緊張感が増し、歌や楽器が次々叫ぶかのように折り重なって、混沌としつつスリリングな展開に。そしてラスト曲「Zikir」。呻き声のような不気味なコーラスに、ダンディな低音ボーカルが渋い声で魅せます。音数少なくも演奏はダークで緊張感に満ち、ゴシックロック的な雰囲気。ですが盛り上がりを待っていたら呆気なく終わってしまいました。
かつてのバウハウスが持っていた近寄りがたい鋭利で狂気的な雰囲気は薄まり、円熟味を帯びて丸くなってしまいました。バウハウスを期待しなければ出来はそこまで悪くありませんし、デヴィッド・ボウイっぽいピーターのボーカルのおかげで個人的には別の魅力も見出せたりします。ですがバウハウスとして聴くにはちょっと物足りない印象は否めません。
編集盤

2013年
Boxセット『5 Albums』に付属していたベスト盤になります。単体ではダウンロード限定販売みたいですね。バウハウスは同時代のインディー系バンドと同様、アルバムに収録していないシングルも多く、人気の高い「Bela Lugosi’s Dead」や「Dark Entries」を収録。またデヴィッド・ボウイやT・レックスといったグラムロックのカバーも聴きごたえがあります。
「Rosegarden Funeral Of Sores」はヘヴィに歪んだギターで開幕。ダブを用いたドラムと淡々としたベースが無機質なリズムを刻み、ピーター・マーフィーの歌も抑揚がなく不気味です。終盤ようやく起伏が出てきて感情が表に出る感じ。「Poison Pen」はケヴィン・ハスキンスの躍動感あるドラムとデヴィッド・Jの硬質なベースが血を沸き立たせます。ギターはキュッキュしててなんか気持ち悪い。ひたすら反復する歌詞も特徴的ですね。続く「Telegram Sam」はT・レックスのカバー。演奏はメタリックで切れ味抜群。そしてピーターの歌は血管ブチ切れだったりおどけてみせたり、表情豊かにマーク・ボランを演じて見せます。「Ziggy Stardust」はデヴィッド・ボウイのカバー。これが実に素晴らしい傑作なのです。原曲に忠実な演奏はモダンなサウンドになったことで本家よりカッコ良いし、ピーターの癖のある歌い方もデヴィッド・ボウイを完璧に真似ていて、全く違和感がありません。「Dark Entries」はスリリングな疾走曲。焦燥感を煽るハスキンス兄弟のリズム隊、ダークで緊迫したダニエル・アッシュのギター、そしてピーターの歌はまくし立てるようで、コーラスも被せてシャウト気味に歌います。鳥肌もので、ポジティブパンクの名曲です。僅か1分半の「Scopes」はダークなイントロで幕を開けますが、強い緊張が漂う楽曲に合いの手が入ると妙なノリの良さが加わります。ノリが良いようで、不気味な焦燥感が同居する変な楽曲です。「The Sanity Assassin」はシリアスな雰囲気が漂うスリリングな疾走曲。ゲートリバーブを用いた1980年代特有のドラム音に、ギャング・オブ・フォーばりのカミソリギターが切り刻みます。低音でメロディを奏でるベースや怒気のある歌もカッコ良い。エキゾチックな香り漂う「Spirit (Single Version)」はここまでの攻撃的な楽曲と異なり、美しいフレーズも出てくるようになります。音が詰め込まれてガチャガチャしているものの、鍵盤とか透明感のある音も聞けます。「Lagartija Nick」は野性味のある楽曲で、疾走気味の演奏にはサックスも加わっています。時折音が割れるかのような激しい側面も見られたり。幽玄で神秘的な「Earwax」はダブを用いたペチペチしたリズムに、歌も含めて強いエコーがかった音が印象に残ります。大きな盛り上がりもなく実験的な楽曲ですね。「Watch That Grandad Go」はパーカッションとカミソリギターがファンキーな演奏を繰り広げます。サックスも加わって賑やかなのですが、狂気じみた歌のせいか不協和音のせいか、怪しげな儀式に出くわしてしまったかのような印象に仕上がっています。ノリは良いのに不気味という…。そしてブライアン・イーノのカバー曲「Third Uncle (Single Edit)」。これがスリリングでカッコ良いんです。イントロから弾けるような躍動感と強い緊迫感が漂い、歌は同じフレーズを反復しながらまくし立てるかのように緊張をどんどん高め、焦燥感を煽ってきます。「Terror Couple Kill Colonel」は音数少ない楽曲で、時折ダニエルが美しいギターを聴かせるのですが、それ以外は民族音楽っぽさもある実験的な演奏を展開します。「In Fear Of Dub」はスリリングな疾走曲。タイトルにもあるように、ダブを用いた武骨なリズムを際立たせていて、そこにエフェクトを強くかけたギターが絡んでくるような楽曲展開。歌も楽器のようにポツリポツリと表れるだけで、メロディといえるものはありません。でもこれが中々カッコ良い。続く「Kick In The Eye (Remix Single)」もリズム隊がメインで、特にベースが際立っておりグルーヴ感抜群。ピーターの歌はデヴィッド・ボウイを想起させます。そして名曲「She’s In Parties (Single Edit)」。イントロからギターが哀愁を誘い、そしてボーカルもアンニュイで憂いに満ちています。内省的で暗く沈んでいくような感覚ですが、幻覚的なサウンドもあって不思議と心地良さも感じられます。「Crowds」はほぼピアノだけの演奏とボーカルによるシンプルで美しい楽曲。ノイジーで攻撃的な楽曲を奏でていたバンドがこういう毒のない楽曲を出すと、そのギャップもあってぐっとくるんですよね。バンドの終わりを感じさせ、切なさを助長します。そんな美しい楽曲に続くのは、恐ろしく狂気じみた楽曲「Paranoia, Paranoia」。淡々としたドラムがひたすら無機質なリズムを刻み続け、そこにSEやノイズが次々と現れては不気味な残響音を聞かせフェードアウトしていきます。聴いていると脳を蝕むかのような恐ろしさがあります。「Spirit In The Sky」は渋くブルージー…なのですが、ミックスをミスしたかのように大音量のベースが異様な雰囲気。歌もだんだんヤケクソ気味になっていっている感じです。そしてラスト曲はデビューシングル「Bela Lugosi’s Dead (Tomb Raider Mix)」。9分半に及ぶ大作で、エフェクトをかけて聴いたこともないような音を出すギターがとにかく印象的。淡々としたリズムに加えて、歌は抑揚のないメロディをなぞり(ピーターの歌い方によって感情が表に出てる感じ)、ダークな雰囲気が漂います。
1979年から1983年までの4年間の活動の軌跡。後年多少丸くなるとはいえ(それでも大衆寄りではありません)、全体的にはカミソリのように鋭利でスリリングな楽曲が詰まっています。
Boxセット
外装:
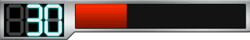
内容:
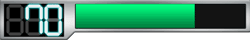
価格:
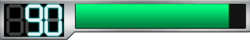
総合:
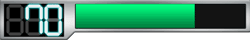
収録作品
| 評 価 | タイトル | 商品情報 |
|---|---|---|
| 70点 | In The Flat Field (暗闇の天使) | 1980年 1stアルバム |
| 65点 | Mask (マスク) | 1981年 2ndアルバム |
| 75点 | The Sky’s Gone Out (ザ・スカイズ・ゴーン・アウト) | 1982年 3rdアルバム |
| 70点 | Burning From The Inside (バーニング・フロム・ジ・インサイド) | 1983年 4thアルバム |
| 80点 | Singles | 2013年 ベスト盤 |

バウハウスの廉価Boxです。他のアーティストでも出ているこの「5 Albums」シリーズはとにかく安い。ただこのシリーズは初回生産分を売り切ったら終わりなのか、アーティストによっては廉価盤なのにプレミアが付いてたり……バウハウスはそこまでの人気がないのか、まだまだ安値で買えます(2020年5月末現在)。気になる作品が3つ以上あればこのBoxセットがお買い得でしょう。
コンパクトな外箱で、各作品はペラペラの薄い紙ジャケットに入っています。その中にはCDが裸の状態で入っているので、保護スリーブは買った方が良いかもしれません。歌詞カードも解説もないので、CD目当てと割り切るべきでしょう。
各作品のレビューは重複のため本項では割愛しますが、解散までの4枚のアルバムとベスト盤を収録しており、これを買えば概ね網羅できますね。再結成後は含まれていませんが、ほぼコンプリートといっても良いのではないでしょうか。どの作品もそれなりの取っつきにくさはあるものの、鋭利でスリリングな楽曲はカッコ良いですし、水準は比較的高めです。
価格は2020年5月末現在で最安2,700~2,800円程度なので、1作品あたり約550円とお買い得です。音源目当てであれば本作を買うのも良いかと思います。
類似アーティストの開拓はこちらからどうぞ。














