🇬🇧 Public Image Ltd. (パブリック・イメージ・リミテッド)
レビュー作品数: 5
スタジオ盤

1978年 1stアルバム
パブリック・イメージ・リミテッド(通称:PIL)は1978年に結成されたポストパンクバンドになります。セックス・ピストルズのツアー中に脱退したジョニー・ロットン改め本名ジョン・ライドン(Vo)が、ジャー・ウォブル(B)とキース・レヴィン(Gt)に声をかけて新バンドを結成。オーディションの末ジム・ウォーカー(Dr)をメンバーに加えて本作をリリースしました。バンド名は「大衆の想像 有限会社」の意味だと思っていましたが、どうやらライドンが「世間一般の(期待するパンクという)イメージの限界」という意味合いで採用したらしいです。パンクで開けた風穴をどんどん突き進み、誰もがやらなかったことへ挑むパイオニア精神のようなものが溢れています。
ロックンロールに回帰し熱い音楽を奏でたセックス・ピストルズに対し、PILはクラウトロック(ドイツのプログレ)やレゲエ等の音楽に影響を受けながら、先鋭的で実験的なサウンドを展開してこれまでのロックを否定しました。前者はマルコム・マクラーレンの仕掛けもあるので、ライドンが本当にやりたかった音楽は後者なのかもしれません。人を食ったような姿勢は、歌メロなんてあったものじゃない歌唱だけでなく、ジャケットにも表れていると思います。『パブリック・イメージ 創刊号』と題された雑誌の表紙のようなアルバムジャケットには、特集ページのように楽曲のタイトルが紹介されていますね。
オープニングの「Theme」では、延々と同じフレーズを繰り返すバックの鈍重なサウンドに、歌メロなんてあったものじゃないライドンの咆哮。この楽曲が9分続きますが、苦行ではなく結構好きだったりします。ウォブルの地を這うようなベースがこの楽曲の軸を作り、炸裂するようなドラム、そしてギターは不協和音を奏でます。続く「Religion I」はライドンが抑揚のない声で淡々と語ります。歌じゃないですね。その内容はキリスト教への批判。続く「Religion II」でベースの低音がズシンと響く重厚な楽曲に不協和音、そしてやはり歌とは無縁の、メロディ無視のライドンのボーカルが強烈です。イヤホンやヘッドホンで聴くと音の鳴る位置があちこち移動していて変な気分です。「Annalisa」では、これまで無縁だったキャッチーさがようやく表れてきます。力強いリズム隊がとてもカッコいいですが、叫び散らすライドンの歌も捨てがたい。
アルバムは後者に突入。本作中最もキャッチーな表題曲「Public Image」。セックス・ピストルズ時代を彷彿とさせる、攻撃的で躍動感のある楽曲です。歌詞ではマルコム・マクラーレンに対する不満をつらつらと並べて「あんたが手に入れたのは俺のパブリック・イメージだ」と主張しています。そして「Low Life」は緊迫感に満ち溢れた疾走曲。レヴィンのギターが警告音のように緊迫した空気を作り出しますが、勢いがあって爽快です。続く「Attack」もかなり攻撃的。メタリックなサウンドに、終始シャウト気味の激しい歌唱で、これもなかなかカッコいいと思います。最後に、レゲエのダブという手法を取り入れた実験的な楽曲「Fodderstompf」で終えます。斬新ながら少し冗長な印象はありますけどね。このダブに傾倒し、次作は重厚なダブサウンド路線となります。
一部にセックス・ピストルズの面影を残しつつも、過激だけど楽しいセックス・ピストルズとは異なり、パンクスを突き放す先鋭的な音楽が展開されます。なお、全編を通してウォブルのベースがサウンドの核となっていて、これがカッコ良い。ロックのその先を模索した先駆者の作品は、緊張感溢れる傑作なのでした。
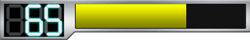
1979年 2ndアルバム
同一の作品ですが『メタル・ボックス』と『セカンド・エディション』という二つの呼び名が存在する作品です。発売当初、ジョン・ライドンの強い拘りで、レコードを特殊な缶ケースに入れて、その名も『メタル・ボックス』の名で数量限定でリリースされました。しかしこの缶ケースの採算が合わず、売れば売るほど赤字になるという代物でした。次いで流通盤として、ぐにょんと歪められた顔がジャケットに描かれリリースされたそれは『セカンド・エディション』つまり「第二版」という、なんとも安直なネーミングでリリースされました。パッケージの違いのみで楽曲は同じなので、お好みの呼び名で呼ぶのが良いでしょう(呼び名としては『メタル・ボックス』の方がよく見かける気がします)。
10分強の大作「Albatross」でアルバムは開幕します。キンキンと耳障りな金切り音を奏でるキース・レヴィンのギターによって、ヘヴィメタルよりもメタリックな仕上がりとなっています。そして、ひたすらに単調なリズムを刻むマーティン・アトキンスのドラムと、ジャー・ウォブルの地を這うようなベースが特徴的。単調だし耳障りな音なのに、ひたすら反復するために妙な中毒性があり、アルバムの中ではこれが一番印象に残ります。続く「Memories」では、次作で顕著となる中東音楽へのアプローチが少し表れ始めています。単調ながらビート感のあるドラムに、怪しげなメロディと張り詰めた緊張感。そしてライドンの抑揚がない歌メロ。独特だけどスリリングです。「Swan Lake」も前曲同様で、ビート感のあるリズム隊に乗るのは少し中東音楽っぽいメロディ。リズム隊のおかげでノリは良いものの、実験的な作風はかなり取っつきにくい印象です。「Poptones」は8分近い楽曲です。ウォブルのベースがうねり、レヴィンのギターは無機質な感覚ですが、全体に漂う気だるげな雰囲気でゆったり聴けます。ただ、聴いていると眠くなる…。続く「Careering」はひんやりとした空気感。リズムを強調したヘヴィなダブは不気味さを強調しています。「Socialist」はインスト曲。SFチックなSEが鳴り響く、単調だけど中毒性のあるダブサウンドです。レヴィンのギターがキンキンと鳴るインスト曲「Graveyard」を挟んで、「The Suit」はやはり淡々とした1曲。ベースが不気味に響き、ライドンの歌は抑揚が無くお経を上げているかのよう。続く「Bad Baby」でテンポアップ。ヘロヘロした歌がなんか気持ち悪いですが、淡々と反復するリズムが結構心地良かったりします。「No Birds」からはようやく聞きやすくなります。ギターは比較的キャッチーなメロディを奏で、リズム隊は躍動感があります。そして「Chant」は後半のハイライト。不協和音を奏でるギターが緊迫感を高め、ライドンの無感情なコーラスが異様な空気を作り出します。ひたすら怖いですがインパクトがあります。最後に「Radio 4」はシンセがメロディを奏でるインストゥルメンタル。これも冷徹で不気味な印象です。
ダブに傾倒した作品です。キンキンとしたレヴィンのギターがメタリックなだけでなく、感情を排したような歌も金属のように無機質。最高傑作に上げる人も多いものの、個人的には何度聴いても中々理解できない作品です。中盤が冗長に感じるのがその原因でしょうか。但し序盤と終盤はインパクトの強い楽曲もあり、駄盤と切り捨てられずに時折聴きたくなる魔力を持っています。
左:『メタル・ボックス』。CDですが、レコード時代の缶ケース入りを再現していますね。
右:『セカンド・エディション』。パッケージにこだわらなければこちらの方が安いです。

1981年 3rdアルバム
ジャー・ウォブルが脱退し、ベーシスト不在で制作することとなった本作。マーティン・アトキンスも解雇となりましたが、ウォブルの脱退を受けて再起用。これまでの2作がウォブルのベースがサウンドの核だったこともあって、苦し紛れの策だったのかもしれませんが、結果として西欧的アプローチを捨てて民族音楽に接近したとても新鮮な作品が出来上がりました。アトキンスの民族音楽的なドラム、ジョン・ライドンのメロディを無視したボーカルも非西欧的です。またキース・レヴィンはギターだけでなくベースの穴埋めやシンセを弾いたり、楽曲によってはドラムも担当しています。
東南アジアとかそういう音楽かと錯覚するような英国の音楽。ライドンは楽器は弾けなかったそうですが、その奇抜で真新しいアプローチは革新的です。なおジャケットの女性はジャネット・リーといい、メンバーにはクレジットされていますが、実際にはほとんど何もしなかったそうです。
オープニング曲「Four Enclosed Walls」からいきなり強烈です。不気味なSE、そして民族音楽のような独特なドラムのリズム。イスラム風のライドンのボーカルで、歌われる歌詞もイスラム的なもののようです。初めて聴いたときに「なんだこれは!」という良くも悪くも強烈なインパクトを植え付けました。とにかく聴いたことのないドラムパターンが癖になります。続く「Track 8」も、ドラムとベースが単調ながらも癖になりそうな独特なリズムを刻み、その上をメロディなんてないギターが鳴り響きます。不気味な緊張感が漂う1曲です。「Phenagen」は古代遺跡で流れていそうな怪しげなイントロから、念仏を唱えるかのような東洋的な雰囲気。不協和音を奏でるギターが時折挿入され、そのたびに拒否反応が出ます。表題曲「Flowers Of Romance」もスネアを用いないドラムが作り出す、プリミティブなサウンドが強烈。ヴァイオリンもバックで不気味な雰囲気を作っていますね。どこぞの部族の音楽なんだ?という印象です。続く「Under The House」はプリミティブなドラムサウンドが力強くて攻撃的な印象。レヴィンとアトキンスの両名が叩いているのだそうです。そこに抑揚のない歌が乗っかり、まるで不気味な儀式に出くわしてしまったかのようです。
アルバム後半は「Hymie’s Him」で幕開け。パワフルなドラムには強いエコーがかかって存在感が更に強調されており、シンセがダークな雰囲気を作ります。不気味です。続く「Banging The Door」はハイハットやスネアの音が出てきて、ようやく(ドラムだけは)西欧的なロックという感じに。しかしドラム以外は相変わらず実験的で不気味な雰囲気が漂い、すんなり受け入れられるサウンドではないですね。「Go Back」では強調されたドラムの裏で金切り音を出す耳障りなギター、そしてライドンの歌も単調。無機質な感じが漂います。そしてラストの「Francis Massacre」なんて野生に帰ってしまったかのような収拾のつかないサウンド。無秩序で異様な緊張感に満ちており、とてもスリリングです。どこを切り取ってもメロディラインなんて存在しません。
パーカッシブなドラムが主導する、非西欧的な音楽へのアプローチ。とにかく先鋭的で緊張感に満ち溢れています。前作同様に聴く人を選びますが、こちらは個人的にはすんなり受け入れられました(最初は戸惑いましたが)。新鮮さに溢れる作品です。
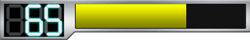
1984年 4thアルバム
アルバム『Commercial Zone』の制作に取り掛かったPILですが、ジョン・ライドンとの意見の相違により、キース・レヴィン(Gt)が脱退。これによりライドン以外のオリジナルメンバーは全員バンドを去ってしまいました。レヴィンと取り組んでいた『Commercial Zone』は全て録り直して本作をリリース。2ndから加入したマーティン・アトキンス(Dr)がギター、シンセベース、キーボード等も兼任し、ライドンもボーカルだけでなくシンセサイザー等を弾いています。またサポートミュージシャンとしてコリン・ウア(Gt)、ルイス・ベルナルディ(B)、リチャード・コトル(Key)、ゲイリー・バーナクル(Brass)も招いて制作しています。
これまで前衛的な音楽でファンを驚かせてきたPILですが、本作では大衆向けのキャッチーなディスコ音楽に。既存のフォーマットにとらわれないパンクの姿勢を期待する人には本作はガッカリだったのか、当時の評価は散々だったそうですが、サウンドは普通に聴きやすくて良いと思います。また全編を通してライドンの歌はハイトーンかつヘロヘロで賛否ありそうですが、これまでと違って「歌って」います。
オープニング曲は「Bad Life」。前作に引き続き民族音楽のようなドラムを聴けますが、これにノリの良いダンスビートとメタリックなベースが加わり、更にホーンも鳴る賑やかな楽曲に仕上がっています。ライドンの歌も、珍しく歌っぽい。キャッチーでノリの良いダンスチューンです。「This Is Not A Love Song」もダンスナンバー。ニューウェイヴらしい華やかなサウンドで、これもキャッチー。ヒット曲(=ラブソング)を要求するレーベル側に対する回答として「これはラブソングじゃない」。でもキャッチーなサウンドなので反骨精神はポーズだけという感じがします。姿勢面ではガッカリだったとしても、曲はこれまでで最も聞きやすく、オススメできる1曲です。続く「Solitaire」はファンキーなナンバー。グルーヴ感抜群のベースがとにかくカッコ良く、ライドンのファルセット気味のヘロヘロ声とピコピコサウンドが幻覚的な世界へと誘います。「Tie Me To The Length Of That」は怪しげな雰囲気が漂う1曲。緊張感はあるものの、前3作のような異様とも言える空気感ではありません。少し暗いサウンドの中でぶつぶつ呟くように歌います。
アルバム後半、「The Pardon」は前作の延長のような楽曲です。アフリカンビートを刻むドラムに、怪しげなメロディ、呪術的な歌などエキゾチックな印象を抱きます。「Where Are You?」はリズムビートにライドンの抑揚のない歌が乗り、それ以外はよくわからない効果音が飛び交います。実験的な感じのダンスナンバーですね。「1981」はパーカッシブなドラムやサウンド面に民族音楽的な雰囲気を残しつつも、スペイシーなSEも鳴ってかなりカオス。ですがノリは良く、ダンスミュージックとして楽しめるのではないでしょうか。ラスト曲「The Order Of Death」はこれまでの楽曲と異なり、ジョイ・ディヴィジョンにも通じる荘厳でダークな雰囲気。それでいながらドラムマシーンを用いたビートや反復するライドンの歌はノリが良いんです。
これまでの実験的な音楽手法を用いてキャッチーなディスコナンバーに仕上げた感じ。PILの中では聴きやすく、一風変わったダンスミュージックといった印象です。賛否両論だそうですが、普通に良作だと思います。
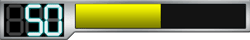
1986年 5thアルバム
提供フォーマットによりタイトルの異なる作品。その名も『アルバム』。レコードは『Album』、CDは『Compact Disc』、カセットテープは『Cassette』と、人を食ったようなタイトルです。ちなみに帯には『Label』と書かれていたのだとか。笑
マーティン・アトキンス(Dr)も去ってしまい、結局ジョン・ライドンのソロプロジェクトになったPIL。ビル・ラズウェルをプロデューサー兼サポートベーシストとして招いています。本作はサポートミュージシャンがとても豪華で、坂本龍一(Synth)、スティーヴ・ヴァイ(Gt)、ジンジャー・ベイカー(Dr)等々。ただその音楽性はハードロックで、ライドンは8年ほど前に「ロックは死んだ」とパンクで自らぶち壊したですが、そのロックに結局回帰してしまいました。ここにPILの限界が見えたわけですが、楽曲はキャッチーで聴きやすいです。
開幕「F.F.F.」で展開されるのはノリの良いハードなロックンロール。ライドンは相変わらずヘタな歌を披露しますが、豪華演奏陣によるヘヴィなサウンドはとてもスリリングですね。続く「Rise」はメロディアスな楽曲で、PILにしてはとても珍しく、歌ものとして聴けます。あとはベースの存在感も凄いですね。この楽曲は南アフリカの反アパルトヘイトで立ち上がったネルソン・マンデラをフィーチャーしたそうです。パーカッションにアフリカンビートが取り入れられていますが、前2作のように露骨ではなく、ごく自然にエッセンスを取り入れています。「Fishing」はジンジャー・ベイカーのドラムが躍動感を生み出します。キャッチーで分厚くゴージャスなサウンドは少しオリエンタルなメロディを奏で、そこに歌っているけど抑揚のないライドンの歌が乗ります。続く「Round」も、キャッチーだけどどこかエスニックな雰囲気が漂います。スティーヴ・ヴァイのギターソロが聴きどころでしょう。
アルバムは後半に突入。「Bags」は反復する呪術的な歌が強烈ですが、その後はノリの良いサウンドを展開。坂本龍一のエスニックなシンセの音色により、少しアジアンテイストの入ったハードロックに仕上がっています。ジンジャー・ベイカーの力強いドラムが作るビートも凄まじい。「Home」はストレートなハードロック。ライドンの歌い方もあってメロディが弱いくらいですかね、他のハードロックとの違いは。トニー・ウィリアムスがドラムを叩きますが、彼もまたパワフルなドラムで圧倒します。ラスト曲「Ease」は8分に渡る大作。重厚な雰囲気で、アフリカンビートや中東風のフレーズなど多国籍な感じです。スティーヴ・ヴァイのギターソロがカッコ良い。
豪華ミュージシャンのおかげで良質なハードロックに仕上がりました。ただPILの独自性は失ってしまい、世にありふれたハードロックになってしまったので、わざわざPILで聴く必要あるのかと言えば「?」が少し浮かびます。
関連アーティスト
ジョン・ライドン(Vo)がジョニー・ロットンを名乗って活動していた伝説的パンクバンド。
キース・レヴィン(Gt)が在籍していたパンクバンド。
類似アーティストの開拓はこちらからどうぞ。
















