🇬🇧 The Stranglers (ザ・ストラングラーズ)
レビュー作品数: 9
スタジオ盤
パンク期
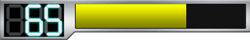
1977年 1stアルバム
イングランド出身のロックバンド、ストラングラーズ。1974年に結成し、パンクムーブメントの最中に頭角を現しました。メンバーはヒュー・コーンウェル(Vo/Gt)、ジャン=ジャック・バーネル(Vo/B)、経営者のジェット・ブラック(Dr)、プログレ畑出身のデイヴ・グリーンフィールド(Key)の4人組。ハードロックやプログレとは一線を画す演奏や振る舞いでパンクとして扱われるものの、他のパンクバンドとは違って既にキャリアを重ねていた(ブラックはデビュー時38歳)のと、メンバーにキーボードが居るのが特徴的です。
アルバムは「Sometimes」で幕開け。ヘヴィなベースを唸らせたり、だみ声で歌うコーンウェルの歌唱スタイルはパンキッシュですが、ハモンドオルガンやミニモーグシンセの音色が異彩を放ち、彼らの独自性を見せつけます。「Goodbye Toulouse」はシンセがスペイシーな音色を奏でる傍ら、ハードなバンドサウンドが迫ります。スリリングな一方で明るくキャッチーでもあり、魅力的な1曲です。続く「London Lady」は2分半の爽快なロックンロール。ノリノリのギターやドラムが勢いをつけ、同じフレーズを連呼するバーネルの歌も耳に残りますね。「Princess Of The Streets」はベースをゴリゴリ鳴らしながら、6/8拍子のゆったりとしたリズムで渋い歌を聴かせます。ブルージーな楽曲で、泣きのギターソロもじっくり聴かせてくれますが、スペイシーな音色を奏でるシンセが若干浮いていて独特な印象。「Hanging Around」はジャムセッションのようなイントロの中で、バーネルのゴリゴリベースが一際目立ちますね。歌も比較的激しめですが、メロディはポップで聴きやすいです。
アルバム後半のオープニングを飾るのは人気曲「Peaches」。硬質なベースリフで始まり、ひたすらミニマルなフレーズを反復します。楽曲の構成は単調でシンプルですが、ファンクっぽいリズムを取り入れていて、聴いていると中毒性があります。「(Get A) Grip (On Yourself)」は先行シングルで、疾走感のある楽曲です。パワフルなドラムと骨太なベースが楽曲を力強く支えつつ、キーボードがフワフワと浮遊感を出したり、遊び心も感じられます。テナーサックスの味付けも爽やかですね。「Ugly」はハモンドオルガンが気持ち良い、ノリの良い楽曲です。バーネルの吐き捨てるような歌はアグレッシブですが、茶化すようなシンセが楽曲をユーモラスに仕上げます。そして8分近くに及ぶ「Down In The Sewer」は4パートから成る組曲。ダーティな演奏を繰り広げ、2分手前くらいから歌パートが始まります。ゴリゴリベースとハモンドオルガンが特に目立ちますね。5分過ぎた辺りからの演奏がダイナミックで良い感じ。終盤は加速して終わります。
アグレッシブな演奏ですが、キーボードの存在が楽曲に彩りを与えてくれます。中々面白い作品だと思います。
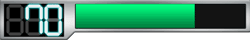
1977年 2ndアルバム
前作から僅か7ヶ月で発表された本作は、前作のセッションで収録されなかった4曲と新録曲によって構成されています。作風としては前作の延長にあります。ボーカルはヒュー・コーンウェル(Vo/Gt)、ジャン=ジャック・バーネル(Vo/B)に加えて、2曲ほどデイヴ・グリーンフィールド(Key)もボーカルを取っています。前作に引き続きマーティン・ラシェントによるプロデュース。
「I Feel Like A Wog」はオルガンと強靭なゴリゴリベースが楽曲の軸を作り、勢い溢れる演奏にコーンウェルのパワフルな歌唱が乗るパンキッシュな1曲です。焦燥感を煽り立て、スリリングでカッコ良いですね。続く「Bitching」はエッジの効いたギターに始まり力強いリズム隊が絡んで、そこにシンセが軽やかさを追加。バーネルのだみ声はドスが効いていて迫力がありますが、楽曲自体はポップで軽快なためキャッチーな印象です。「Dead Ringer」はグリーンフィールドのボーカル曲ですが、ストラングラーズは揃いも揃って野太いだみ声ですね。笑 リズミカルな演奏に陽気なコーラスで楽しめます。「Dagenham Dave」は軽快で勢いのある楽曲で、ノリが良くて楽しめます。演奏は骨太で歌唱も野太いですが、メロディはポップで明るいので聴きやすいです。「Bring On The Nubiles」はイントロもなくいきなり歌で始まります。声にエフェクトをかけたりスペイシーなシーケンサーを用いたりして、パンキッシュですが既にニューウェイヴを先取りしたような趣です。「Something Better Change」は独特のリフが特徴的で、カラフルな鍵盤や骨太なベースが絡んで陽気な楽曲に仕上げます。ボーカルはがなるようにパワフルですが、メロディは中々ポップです。
アルバム後半は表題曲「No More Heroes」で幕を開けます。イントロからノリノリで躍動感に溢れており、力強さがありますが、カラフルなキーボードがポップでコミカルな感覚を強めます。コーンウェルがだみ声で歌うメロディも、口ずさみたくなるようなポップさがあります。続く「Peasant In The Big Shitty」はジェット・ブラックのドラムが変則的(4/4+5/4拍子?)なリズムを刻み、グリーンフィールドの歌も演劇的で、ひねくれていてコミカルです。変なんですが中毒性のある楽曲です。「Burning Up Time」はバッキバキのベースに加え、バーネルの吐き捨てるような歌もアグレッシブです。でも茶化すようなシンセの音色がコミカルさをプラスして、全体的に楽しい空気に変えてくれます。「English Towns」はアップテンポのノリノリな楽曲です。間奏で力強く刻む太鼓がテンション上がりますね。そして最後に「School Mam」。子どもが遊んでいるかのような効果音から集合をかけるようなベルをチリンチリンと鳴らし、そこから力強く足踏みするかのような骨太な演奏を繰り広げます。陽気でコミカルかつ3分台でサクッと終わる他のアルバム曲とは違って、7分近くある上に強い緊張が張り詰めており、ひりついていてスリリングかつハードな楽曲です。
グリーンフィールドのオルガン/シンセとバーネルの骨太なベースが織り成す、パワフルだけどポップな演奏。楽曲も粒揃いで良質な作品です。

1978年 3rdアルバム
前作から約8ヶ月と、相変わらず早いペースで制作されました。制作陣も変わらずで、本作までマーティン・ルーシェントがプロデュースしています。本作では変拍子をはじめ実験的なアプローチを強めています。ヒュー・コーンウェルのボーカル曲が前半「White Side」に集中していて統一感がありますが、後半「Black Side」にはジャン=ジャック・バーネルやデイヴ・グリーンフィールドもボーカル参戦し、バラエティ豊富ですがやや散漫になります。
まずは「White Side」と銘打たれたレコードでいうA面。「Tank」は、目の覚めるようなパワフルなイントロに吹き飛ばされますが、そこにグリーンフィールドの鳴らすピロピロ鍵盤が絡んで特有の浮遊感や躍動感を生み出します。勢い溢れる楽曲で、途中爆発の効果音を挟んだりしてパワフルな印象ですね。続く「Nice ‘N’ Sleazy」はミドルテンポの楽曲で、バーネルのゴリゴリベースが際立ちます。鍵盤が無ければかなり武骨でシリアスな雰囲気ですが、スペイシーなシンセサイザーやシーケンサーが茶化すような感じに楽曲を和らげます。「Outside Tokyo」は3拍子を刻む哀愁漂う楽曲で、陰鬱でメランコリックなメロディを歌います。コーンウェルの歌はこの楽曲ではかなりヘタウマな印象ですが、少しレトロ感のある哀愁のメロディが中々に魅力的なんです。僅か2分で終わるのが物足りないですね。「Hey! (Rise Of The Robots)」は前曲の陰鬱な空気を吹き飛ばす、勢い溢れるパンキッシュな楽曲です。キレのあるギターを皮切りに繰り広げられるテンポの速い演奏に、コーンウェルのシャウト気味の力強いボーカル。そして時折サックスも楽曲を賑やかに盛り上げてくれます。「Sweden (All Quiet On The Eastern Front)」は骨太なベースがゴリゴリと勢いをつけます。疾走感のあるパンキッシュな演奏でシンプルかつ爽快ですが、中盤でリズムチェンジしてガラリと雰囲気を変えると、そこから演奏パートに突入。終盤で再び歌が始まると、序盤のメロディが戻ってきます。「Toiler On The Sea」はスリリングな楽曲で、イントロが2分ほど続くのでインストゥルメンタルかと思いきや、コーンウェルの野太い歌が途中から始まります。力強くて疾走感のある演奏に、ピロピロと軽やかなシンセを鳴らす、勢いのある楽曲です。
アルバム後半は「Black Side」と銘打たれています。「Curfew」は一部に7/4拍子が組み込まれた楽曲で、独特の楽曲構成にサイケデリックなキーボード、そこにバーネルの調子外れな歌が絡んでグワングワン揺さぶってきます。「Threatened」はジェット・ブラックの刻むドラムが行進するかのように気持ちの良いリズムを刻みます。コーンウェルとバーネルので絶妙にハモれていない歌が独特の印象。続く「In The Shadows」は超重低音を爆音で鳴らすベースに、音響効果を加えたギターなど実験的なサウンドが繰り広げられます。テンションの低い歌はベース音にかき消されそうなほど。「Do You Wanna」はリードベースというべきか、ベースが主旋律を刻んでいます。ドラムもタムの活用でダイナミックな印象。そしてグリーンフィールドが歌うんですが、演劇的というかコミカルな印象を受けます。「Death And Night And Blood (Yukio)」のタイトルは、三島由紀夫の『仮面の告白』のセリフからの引用。ミドルテンポの演奏に乗るバーネルの歌は渋いですが、合いの手がノリノリです。ラスト曲は「Enough Time」で、ヘヴィで不穏な雰囲気を醸すバンド演奏と緊張に満ちた歌、それでいてテクノポップ風のキラキラしたシンセが中々にミスマッチ。終盤は執拗なくらいに反復する歌に狂気を感じます。ニューウェイヴ全開です。
アルバム前半は疾走曲が多くて爽快で、そこに陰鬱な「Outside Tokyo」がアクセントとなって緩急をつけています。後半は実験的な色合いが強いです。前半「White Side」の方が聴きやすいですね。
ニューウェイヴ化/ポップ化移行期

1979年 4thアルバム
前作までのプロデューサーであるマーティン・ルーシェントの手を離れ、本作はエンジニアのアラン・ウィンスタンリーとストラングラーズによる共同プロデュース作品です。冒頭2曲とアートワークは北欧神話からの引用だとか。この頃にはすっかりパンク色は抜けて、内省的かつシンセをバリバリに活用したポストパンク/ニューウェイヴ的な楽曲を展開します。
アルバムはインストゥルメンタル「Longships」で幕を開けます。僅か1分強ですが、テンポの速い3拍子を刻んで高揚感を煽り立てます。続いてタイトル曲「The Raven」。これも1分くらいの比較的長めのイントロもあり、前曲と続けざまにインストゥルメンタルかと錯覚します。ボーカルはジャン=ジャック・バーネルによるものですが、前作までのようなドスの効いた野太い歌唱は控えて、囁くようなハスキーな歌唱で歌います。全体的に哀愁が漂う楽曲です。「Dead Loss Angeles」は爆音ベースが楽曲を支え、ヒュー・コーンウェルが無感情に淡々と歌います。無機質でミニマルなニューウェイヴ特有の楽曲スタイルですが、地味に中毒性があるんですよね。続く「Ice」はオルガンが冷たい雰囲気を作り、ジェット・ブラックのドラムが焦燥感を掻き立てます。シンセサイザーのチープな音色が昔のゲーム音楽を想起させ、これがヘヴィな演奏に合わさることでボスステージに挑むかのようなシリアスな空気感があります。笑 そういう楽曲ではなく、切腹をテーマにした楽曲だそうです。「Baroque Bordello」は4分弱のうちの1分半をイントロが占めます。デイヴ・グリーンフィールドによる鍵盤がそうさせるのかレトロな雰囲気で、そしてメランコリックな哀愁に満ち溢れていて、歌が始まっても暗い空気は晴れません。そしてバーネルの歌う「Nuclear Device (The Wizard Of Aus)」は前作までのような躍動感に溢れています。演奏はハードですが、テクノポップ風のピコピコシンセが楽曲を装飾することでパンク色は薄まっています。哀愁を見せたかと思えば急にキレッキレになる間奏も中々スリリングです。
アルバム後半のオープニングを飾る「Shah Shah A Go Go」は、イラン革命について歌った楽曲です。チープなシンセがレトロゲーム音楽のような音を鳴らしつつ、ギターやベースは切れ味鋭い演奏でザクザク刻みます。歌は抑揚が少ないですが、時折連呼する「Shah shah a go go」は耳に残りますね。続く「Don’t Bring Harry」はピアノを用いた憂いたっぷりの演奏で感傷的な気分にさせます。歌も暗く沈んでいて、救いのない暗さに満ちています。間奏のギターも泣きのメロディを披露。「Duchess」はシングルヒットした楽曲です。勢いのあるノリの良い楽曲で、カラフルな鍵盤がポップさを加えます。キャッチーですが歌はメロディアスで少し切ないですね。「Meninblack」はバーネルの声を加工して、キーを上げた変な声が特徴的です。パーカッションの音色や靄のかかったようなエフェクトがプリミティブかつ幻覚的な雰囲気を醸し出しています。そして最後の「Genetix」はグリーンフィールドのボーカル曲。ビート感の強いリズム隊に乗せて、チープなシンセとポップなメロディ(歌い方はひねていますが)で楽しませます。リズミカルな間奏で盛り上がり、ラストは力強くて晴れやかな印象で終わります。
ニューウェイヴ色が強まりましたが、個人的にはパンク時代よりも好みです。鴉のジャケットアートもクールでカッコ良いですね。

1981年 5thアルバム
初のセルフプロデュースとなる本作は、難解なコンセプトを持ちます。ダークでゴシックな雰囲気を取り入れつつ、シンセポップ的なアプローチが目立ちます。後期ジョイ・ディヴィジョン/初期ニュー・オーダーを想起させます。ヒュー・コーンウェルが後に振り返って本作をお気に入りに挙げていますが、残念ながら商業的には失敗した作品でした。日本では本作で見切られパンクバンドとして扱われますが、本国英国では次作以降人気を獲得してポップバンドとしての地位を得ることになります。
アルバムの幕開けとなる、インストゥルメンタルの「Waltzinblack」。シンセを活用して不気味なワルツを展開。ダークな雰囲気ですが、チープな音色はレトロゲームのような懐かしさを覚えます。後半になると、悪魔がニタニタと笑うかのように気味の悪い笑い声が響き渡ります。「Just Like Nothing On Earth」はコンピュータサウンドのようなスペイシーで無機質な効果音が流れたかと思えば、ドラムとベースが強烈なビートを放ちます。コーンウェルの歌は抑揚をつけずにテンション低い印象ですが、響き渡る重低音が緊張を高め、かなりスリリングです。加工してキーを変えたコーラスが奇妙な感じ。「Second Coming」はひねていますがキャッチーな楽曲です。リズミカルな演奏が高揚感を煽り、歌メロもポップなようで、でもどこか変な感覚も強くて印象に残る楽曲です。ニューウェイヴ的ですが、終盤のオルガン速弾きや幻覚的なコーラスにプログレ・サイケ感もありますね。「Waiting For The Meninblack」はシリアスで暗鬱な雰囲気が漂い、ジェット・ブラックの野性味あるドラムが終始焦燥感を煽り立てます。ギターの弾くメロディはエキゾチックな感じ。コーンウェルによる、執拗に反復する歌詞がひたすら不気味です。そして「Turn The Centuries, Turn」は再びインストゥルメンタル。深く沈んだ冷たく暗鬱な空間に、オルガンのようなシンセがレクイエムのような不気味な雰囲気を助長し、やるせない気分にさせます。ただ、生ドラムに人間味や温かさが微かに感じられて、それが唯一救いでしょうか。
アルバム後半はキャッチーな「Two Sunspots」で幕開け。前半の暗い空気が嘘のように、ピコピコ陽気なシンセやリズミカルな演奏、ヘタウマだけどキャッチーな歌メロが楽しげに、救いの手を差し伸べます。「Four Horsemen」はデイヴ・グリーンフィールドが歌う楽曲です。ブリブリと唸るベースが強烈で、シンセがカラフルに彩ります。トリッキーなリズムや耳に残るフレーズを繰り広げます。「Thrown Away」はダンサブルなリズムビートや骨太なベース、淡々としたキーボードにキラキラしたシンセが、ノリノリで楽しい空気を作り出します。ボーカルはジャン=ジャック・バーネルですが、ノリの良い演奏とは対照的にテンション低く歌います。「Manna Machine」はキーボードが様々な音を奏でて、スペイシーな浮遊感を生み出しつつも、エキゾチックなフレーズも聞こえます。歌は呟くようにローテンションです。ラスト曲「Hallow To Our Men」は、3分台の楽曲が多い本作中ではかなり長い約7分半の楽曲です。冒頭で哀愁を纏いつつもピコピコとリズミカルなテクノポップを聴かせると、ダークでメランコリックなメロディだったりリズムチェンジを多用してプログレのような楽曲を展開。演奏に浸りきっていると、3分手前でやる気のない歌が唐突に始まります。中盤でビートが力強くなって躍動感が増し、終盤はシンセが悲壮感のあるメロディを乗せてメランコリックに。最後は上昇音で終わります。
アルバム前半はひたすらダークで重く沈んで、後半はダンサブルなシンセポップで持ち直します。聴きごたえのある名盤です。
叙情性とポップの融合

1981年 6thアルバム
バンドと、エンジニアのスティーヴ・チャーチヤードによる共同プロデュースとなる本作。「愛」をテーマにした楽曲が並びますが、パリ人肉事件という実際に起きた猟奇殺人をテーマにしたタイトルトラックをはじめ、一筋縄ではいかない様々な愛のかたちを表現します。ストラングラーズ屈指の名曲「Golden Brown」を収録し、件の楽曲のシングルヒットに後押しされてアルバムは全英11位にまで浮上しました。
オープニング曲「Non Stop」は、デイヴ・グリーンフィールドの弾くリズミカルで跳ねるようなパイプオルガンがとても心地良いですね。リズム隊も躍動感に溢れていて、とてもキャッチーな印象です。そしてヒュー・コーンウェルの歌は、落ち着いていて優しいです。続く「Everybody Loves You When You’re Dead」は鍵盤がこの時代特有の陰りを見せつつ、ジャン=ジャック・バーネルによる骨太なベースがくっきり際立っています。メランコリックですが躍動感もあります。「Tramp」はコーンウェルの甘い歌声にビートルズのようなポップセンスを感じました。爽やかでメロディアスなサビメロを、カラフルな鍵盤や勢いある演奏が引き立てて、強く印象に残ります。ブリブリ唸るベースや、ジェット・ブラックのドラム捌きも魅力的ですね。名曲だと思います。そして「Let Me Introduce You To The Family」は力強く明瞭なビートを刻むドラムを軸に、ギターやキーボードがガチャガチャとノイズを鳴らしています。演奏はミニマルですが、シンプルな歌は結構キャッチーな印象で耳に残ります。「Ain’t Nothin’ To It」は、力強いビートと抑揚のない歌が対照的。無機質さとダンサブルな躍動感を両立しつつ、変な歌も併せ持つひねくれた楽曲ですね。続いて「The Man They Love To Hate」はバーネルが歌います。ダイナミックで野性味のあるドラムに支えられ、焦燥感に満ちてスリリングな楽曲は憂いも帯びています。
後半に突入。「Pin Up」はピコピコシンセが気持ち良いポップソング。明るくノリの良い演奏に乗る、コーンウェルの優しい歌声はキャッチーな印象です。「It Only Takes Two To Tango」はパワフルなリズム隊が小気味良くて、思わず踊り出したくなります。演奏はニューウェイヴ的なひねくれ具合ですが、歌メロはポップで、コーンウェルとバーネルがハモったりしながら歌います。そして「Golden Brown」は全英2位を獲得した、最大のヒット曲です。6/8拍子を軸に時折違う拍子を混ぜてフックをかけながら、基本的には緩やかなワルツに仕上げています。チェンバロを用いたバロックポップで、哀愁に満ちたメランコリックなメロディを甘い歌声で届けてくれる、極上のポップソングです。ちなみに麻薬について歌われているのだとか。続く「How To Find True Love And Happiness In The Present Day」は少し怪しげなシンセポップ曲です。シンセサイザーがキャッチーな音色で装飾しつつ、ラテンっぽいパーカッションや淡々としたベース、低いテンションの歌が独特の空気感を作ります。最後にタイトル曲「La Folie」。前述のとおり衝撃的な猟奇殺人がテーマになっていますが、演奏はそんなテーマとは無縁といった感じにゆったり穏やかで、浮遊感があって恍惚に浸るようです。全編フランス語歌詞で、フランス系英国人のバーネルが歌いますが、低いトーンで抑揚もないので語りに近い印象です。
欧州的な哀愁を持ち、メランコリックで叙情的でありながらも、ポップさやキャッチーさがあってとても聴きやすいです。
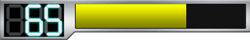
1983年 7thアルバム
前作に引き続いてバンドとスティーヴ・チャーチヤードの共同プロデュース体制です。全体的に落ち着いた雰囲気に仕上がっており、電子ドラムやアコギの多用が特徴的です。前作を上回るヒットとなり、全英4位を獲得しました。
6分超の「Midnight Summer Dream」でアルバムは幕を開けます。ぼんやりと靄のように響き渡るメランコリックなシンセサイザーや、低いトーンで語るようなヒュー・コーンウェルの歌はダウナーで感傷的な気分を誘います。ジェット・ブラックによる電子ドラムは躍動感があるんですけどね。「It’s A Small World」はアコギとドラムマシンを活用したダンサブルな楽曲です。デイヴ・グリーンフィールドによるチープなシンセやメランコリックな雰囲気も含めてニュー・オーダーの「Blue Monday」っぽい印象を受けました。続く「Ships That Pass In The Night」はジャン=ジャック・バーネルのリードベースと呼べるくらい前面に出たベースをはじめ、電子ドラムやシンセがダンサブルな演奏を繰り広げます。歌は淡々としていますが、サビはメロディアスな印象です。「European Female (In Celebration Of)」は骨太なベースにリズミカルなドラムがダンサブルなビートを刻み、アコギはラテンっぽいフレーバーをまぶします。バーネルが歌う楽曲ですが、囁くような歌はあくまで飾りで、ミニマルな演奏がメインといった感じでしょうか。
アルバム後半のオープニングは「Let’s Tango In Paris」。6/8拍子のゆったりとしたワルツを刻み、耽美ですが陰りのある楽曲を繰り広げます。ドラムの出番が少ないですが、出てきたかと思えばコクトー・ツインズばりに強いエフェクトをかけて残響が凄いことになっています。「Paradise」はパーカッションの活用によりトロピカルな雰囲気もありますが、全体的にはメロディアスで憂いを感じさせます。続いて「All Roads Lead To Rome」。メランコリックですが、ダンサブルな演奏はキャッチーで、メロウで落ち着いた楽曲が多い本作の中では取っつきやすい楽曲です。シンセが分厚いですね。「Blue Sister」は緊張が立ち込めるスリリングな楽曲で、キレが鋭くて焦燥感を掻き立てられます。コーンウェルの憂いのある歌も中々良いですね。最後の「Never Say Goodbye」はスパニッシュっぽいフレーズが組み込まれたダンサブルな楽曲です。でも全体的には暗く重たい空気が漂います。
全体的に暗鬱で、加えてメロウな楽曲が多くて前作ほどのキャッチーさが無くなりました。ですが終盤にはキレのある楽曲が並びます。














