🇬🇧 Pink Floyd (ピンク・フロイド)
レビュー作品数: 18
目次
ピンク・フロイド紹介動画
動画にまとめていますので、ぜひご視聴ください!
スタジオ盤①
シド・バレット時代 (サイケデリックロック)

1967年 1stアルバム
ピンク・フロイドは英国のプログレッシヴロックバンドで、現在までに2億3千万枚以上を売り上げるモンスターバンドです。1965年に、建築学校の同級生だったロジャー・ウォーターズ(B/Vo)、リック・ライト(Key)、ニック・メイスン(Dr)の3人でバンドを結成。バンド名を変えながら、友人のシド・バレット(Gt/Vo)を迎えてピンク・フロイドに改名。1967年にデビューしました。
本作のプロデューサーはノーマン・スミス。収録曲の大半が天才シド・バレットの作で、トリップ感が凄まじい仕上がりになっています。バレットはドラッグにまみれていて、ドラッグ体験がこのような狂気的な楽曲を生んだのかもしれません。ピンク・フロイドは後に8thアルバム『狂気』という大傑作を生みだしますが、作品の中身で言えば『狂気』という邦題は本作の方が適している気もします。
1曲目の「Astronomy Domine」から怪しさ全開で、浮遊感のあるスペイシーなサウンドで、聴く人を一気に別の世界に連れ去ります。宇宙を旅しているのでしょうか。そして凄まじい緊張感を持っています。続く「Lucifer Sam」はギターがカッコいい。狂気的なサウンドの中に妙なポップさが同居していて、意外と聴きやすいです。キラキラとした「Flaming」に美しさも感じながら、「Pow R. Toc. H」で強烈なパンチを食らってノックアウト。冒頭の「キャッキャーッ!トイトイ~」という野性味溢れるジャングルでしょうか。冒頭の奇声が過ぎ去った後、何事もなかったかのように淡々としたピアノ。中盤で奇声が再び出てきて、緊張が走ります。…とにかく楽曲にとてつもない狂気を感じます。変な歌メロの「Take Up Thy Stethoscope And Walk」は中盤のオルガンソロが荒れ狂い、緊張感が凄い。そしてインストゥルメンタルの名曲「Interstellar Overdrive」。10分近い大作です。よく分からない演奏が繰り広げられますが、異様な緊張感を放ちます。そんな狂気的な楽曲が並ぶ中、「Chapter 24」では美しいメロディと優しいサウンドを聴くことができます。ラスト曲の「Bike」もヘンテコですが妙に耳に残るメロディ。でもラストはガチャガチャとよくわからない音を立て、不気味な笑い声で終わります。
プログレッシヴロックの雄として名を馳せるピンク・フロイドですが、本作はバリバリのサイケデリックロック。後の作品とは全く毛色の異なる作品ですが、これはこれで優れた名盤なんですよね。
なお本作制作途中から、バレットは過度なドラッグ摂取により奇行が目立ち始め、バンドの活動に支障をきたすようになりました。そのためバレットは本作発表の翌年にはバンドを離れることになりますが、カリスマ的フロントマンを失ったピンク・フロイドは、その後の方向性を模索しながら実験的な作品を作り上げるようになります。
実験音楽時代
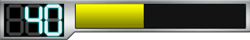
1968年 2ndアルバム
ドラッグの過剰摂取でまともな状態ではなかったシド・バレット。新ギタリストにデヴィッド・ギルモア(Gt/Vo)を迎え、制作を始めました。バレットはいくつかの楽曲を制作してはいますが、制作途中で脱退。残されたロジャー・ウォーターズ(B/Vo)、リック・ライト(Key)、ニック・メイスン(Dr)とギルモアの4人の固定メンバーで、実験的な作品を作りながら名作を生み出していくことになります。
ジャケットアートにはデザイナー集団のヒプノシスが担当。ヒプノシスは本作よりピンク・フロイドの数多くのジャケットアートを手掛けることになり、抽象的なジャケットアート群の中にはジャケ買いしたくなるような強烈なインパクトのあるものも多いです。ですが本作はさほどインパクトはなく、抽象的でなんかよくわからないジャケットです。
前作同様にノーマン・スミスのプロデュース。全7曲で、12分の大作1曲を除けば3~5分半くらいの楽曲が並びます。
スペイシーで浮遊感のあるサイケデリックな楽曲「Remember A Day」が心地よい感じです。またウォーターズ作の「Set The Controls For The Heart Of The Sun」は、静かで神秘的なサウンド。霊的な雰囲気を漂わせています。反復されるフレーズに妙な緊張感が漂っていて、癖になります。「Corporal Clegg」では変なボーカルが聴けますが、これはメイスンが歌っているのだとか。表題曲「A Saucerful Of Secrets」はギルモアが初参加した楽曲で、戦争を表現したというこの曲は12分に渡るインストゥルメンタルです。戦争というよりは不気味なホラーのような雰囲気を感じます。中盤の民族的なリズムの上でよくわからないサウンドが鳴る前衛的なアプローチ。プログレの片鱗を見せ始めます。
前作から引き続きのサイケデリックロックと、プログレッシヴロックの萌芽のような前衛的な楽曲が入り乱れて、アルバム全体の統一感はありません。所々耳に残るところもありますが、正直よくわからない楽曲も多いです。聴き込めば何か掴めるのかもしれませんが、ピンク・フロイドは名盤が多いから、他の作品に手が伸びてしまうんですよね…。
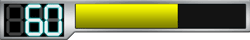
1969年 3rdアルバム
バルベ・シュローダー監督の映画『モア』のサウンドトラックとして制作された本作。なお3年後にも同監督の映画のサウンドトラックを担当し、『雲の影』を発表することになります。
ピンク・フロイドのセルフプロデュースとなる本作。制作は僅か8日間で、ライブ活動を精力的に行う傍ら、ライブで発表した楽曲を流用して本作の制作に至ったそうです。
オープニング曲「Cirrus Minor」は鳥のさえずりから始まります。タイトルのMinorよろしく、ダウナーな雰囲気の弾き語りの後、徐々にオルガンや浮遊感溢れるSEによって幻想的なサウンドへ変貌していきます。続く「The Nile Song」は一転して、ガレージロックばりのノイジーなサウンドが炸裂するヘヴィな1曲。ピンク・フロイドに似つかわしくない意外な1曲ですが、非常にスリリングです。シャウト気味のボーカルはデヴィッド・ギルモアによるものです。楽曲自体はロジャー・ウォーターズの作で、彼のベースも良い味を出しています。「Crying Song」はしっとりとして哀愁漂う1曲で、アコギ主体のシンプルなサウンドに囁くような歌声が染み入ります。2分強のインストゥルメンタル「Up The Khyber」は、ニック・メイスンのドラムとリック・ライトのピアノが中心となってスリリングな演奏を聴かせます。続く「Green Is The Colour」は牧歌的な楽曲。ほのぼのしていて優しい雰囲気。「Cymbaline」はメロディアスな楽曲で、シンプルなサウンドゆえにメロディの良さが引き立ちます。1分強のインストゥルメンタル「Party Sequence」はパーカッション主体の民族音楽的な楽曲を聴かせます。
レコードでいうB面は「Main Theme」で開幕。神秘的で、アラブ風の少し怪しげな雰囲気も纏ったインストゥルメンタルです。続く「Ibiza Bar」は「The Nile Song」のようにヘヴィな楽曲で、ドラムが暴れ回ります。ブルージーな「More Blues」と、SEによってどこか不気味で神秘的な「Quicksilver」とインストゥルメンタルが続きます。僅か1分の「A Spanish Piece」はスパニッシュ風のギターに乗せて独り言のような語り。そして「Dramatic Theme」は単調ながら浮遊感の溢れる1曲。後半は前半ほど魅力的な楽曲はないものの、後の大作主義の片鱗が表れています。
サントラだからといって敬遠していましたが、意外と良い楽曲が揃っていて聴きごたえがあります。荒々しい「The Nile Song」と「Ibiza Bar」が異色のナンバーですが、これらが作品にスリルを持ち込み引き締まっています。
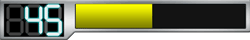
1969年 4thアルバム
ライブ盤とスタジオ盤が組み合わさった2枚組の作品です。ノーマン・スミスとピンク・フロイドの共同プロデュース。
1枚目はライブパートで、どれも10分近い演奏になっています。正直「よくわからないけどなんか凄い」というのが感想です。即興的で理解しがたい世界ですが、所々で非常にスリリング。「Astronomy Domine」で開幕。ハイハットを連打するニック・メイスンのドラムがスリルを生み出します。また、このライブの時点でギターはシド・バレットではなくデヴィッド・ギルモアに代わっていますが、サイケデリックな音色で、怪しげでトリップ感のあるサウンドを展開します。続いて「ユージン、斧に気をつけろ」の邦題で知られる「Careful With The Axe, Eugene」。静かで単調な序盤から徐々に迫り来る不気味さと、ロジャー・ウォーターズの絶叫。狂気じみていて、恐怖感すら覚えるスリリングな楽曲です。後半はやや冗長。続く「Set The Controls For The Heart Of The Sun」は民族音楽的で、リック・ライトの中東風のオルガンが怪しげな雰囲気を作ります。静かな序盤から徐々に盛り上がって爆音に変わっていく展開は非常にスリリング。後半は浮遊感漂うサウンドを展開します。13分に渡る「A Saucerful Of Secrets」はインプロビゼーション大会といった感じ。
2枚目はスタジオパートで、メンバーそれぞれのソロ作を収録しています。まずはライト作の「Sysyphus」。CDではPart 1~4まで分かれています。時折出てくるメロトロンが恐怖感を煽りますが、全体的に実験的かつ難解でよくわかりません…。続く2曲はウォーターズ作で、まずは「Grantchester Meadows」。鳥のさえずりのSEが煩わしいほど終始鳴り響く中、アコギ主体の静かな歌はほのぼのとしています。次は「Several Species Of Small Furry Animals Gathered Together In A Cave And Grooving With A Pict」、邦題は「毛のふさふさした動物の不思議な歌」で、その奇怪なタイトルからしてプログレ。楽器を使わず効果音だけで表現したこの楽曲はジャングルのようで、狂気じみた雰囲気が不気味です。続いてギルモア作の「The Narrow Way」。3部から成る楽曲で、Part 1は陽気なアコギが聴ける、本作では数少ない癒し楽曲でしょう。Part 2でおどろおどろしいサイケデリックな作品になりますが、Part 3でメロウな演奏に優しい歌を聴けます。最後はメイスン作の「The Grand Vizier’s Garden Party」。これも3部から成る楽曲です。フルートの音色が美しいですが、大半がドラムソロ的な内容です。
所々スリリングなパートにハッとさせられますが、難解でよくわからない部分も多いです。ピンク・フロイドの全作品で最も実験的な作品かもしれません。

1970年 5thアルバム
ピンク・フロイドの初期の傑作です。タイトルの『Atom Heart Mother』とはペースメーカーを入れた母親を書いた新聞記事の見出しから取ったそうです。邦題はそれぞれの単語をただ直訳しただけの『原子心母』。安直なネーミングなのですが、意味不明な邦題が想像力を掻き立てるというか、これは良い邦題だと思います。ちなみにMr.Childrenの『Atomic Heart』は、本作から名前を取ったのだとか。
ヒプノシスによるジャケットアートも有名で、プログレと言えば真っ先に挙がるジャケットの一つでもあります。見返り美人ならぬ見返り乳牛はインパクトがありますが、この牛にはルルベル3世という名前がついています。
表題曲「Atom Heart Mother」は全編インストゥルメンタルで、トータル24分弱の大作で、これ1曲でレコードでいうA面を丸々占めています。管楽器が鳴り響いて厳かな雰囲気を醸し出しますが、意外と耳に残るキャッチーなメロディです。これが主題として奏でられ、それをバイクのエンジン音で蹂躙するシュールさ。聴き進めていくと、オペラのようなコーラスパートや、オルガンやギターが主導するロック的なパートもあります。また管楽器の主題が現れたかと思えば、不協和音が鳴り響く不気味なパート。前衛的な楽曲で、一聴すると支離滅裂なようですが、よく聴くと同じメロディが何度か出てきてエンディングへと収束していきます。フィナーレは感動ものです。聴き終えた後の充実感が素晴らしい1曲です。
レコードでいうB面は牧歌的な楽曲が並びます。「If」はロジャー・ウォーターズ作の楽曲。アコースティックギターで優しく奏でられるこの楽曲は「もし僕が白鳥だったなら 飛び立ってしてしまうだろう」という「もしも」な歌詞を羅列した、繊細で内省的な楽曲です。ウォーターズは後にバンドを支配し、エネルギーを外に向けて社会批判的な歌詞で周囲に毒を振り撒くことになりますが、この時点では誰がそんな未来を想像できたでしょうか。続く「Summer ’68」はリック・ライトの作。ビートルズにも通じるポップなメロディで歌います。静かなピアノが主体ですが、徐々に盛り上がり、ブラスがキャッチーなサウンドを奏でます。「Fat Old Sun」はデヴィッド・ギルモア作。アコギで静かに歌いますが、他の楽曲と比べると少し弱いかな。そしてメンバー3人の作品が続きましたが、「Alan’s Psychedelic Breakfast」はニック・メイスン作…ではなく4人全員の作。朝食準備中のキッチンの光景を切り出したような効果音から、ピアノを中心に明るくコミカルなメロディを奏でます。またも効果音だけのパートを挟んで、次はアコギが美しく優しいメロディを奏でるパートへ。ジューシーで美味しそうな効果音を挟んで、オルガンとピアノが主体に。そして水道のポタポタという効果音で終えます。美しいメロディとシュールなアプローチのギャップが強い前衛的な1曲です。
ジャケットアートに惹かれて聴いてみると、よくわからない前衛的な楽曲に戸惑うことでしょう。しかし聴き込むと人を惹きつけて離さない魅力も内包した名盤です。

1971年 6thアルバム
ヒプノシスによる良くわからないジャケットアートは、広げてみると耳に広がる波紋のように見えます。これはハイライトとなる「Echoes」の世界観を表しているかのようです。
オープニング曲である「One Of These Days」は「吹けよ風、呼べよ嵐」の邦題の方が有名でしょうか。バッキバキのベースリフが終始リードするインストゥルメンタル曲です。ベースはロジャー・ウォーターズだけでなくデヴィッド・ギルモアも弾いています。そしてハモンドオルガンが幻想的な世界観を作り出します。中盤からはエレキギターも暴れ回るアグレッシブな1曲です。「A Pillow Of Winds」は一転してアコースティックギターを主軸に、静かな雰囲気の中でギルモアが優しく歌います。牧歌的で優しい「Fearless」もシンプルながら、ギターの奏でるメロディは耳に残ります。ラストでは何故かサッカーの歓声が流れます。「San Tropez」は地味な楽曲ですが、終盤のジャズ風のピアノが洒落た雰囲気を作り出していて良い感じ。「Seamus」は実験的な楽曲で、犬の吠える声が所々挿入されています。
そしてレコード時代はB面を丸々占めていた23分半に渡る大作「Echoes」。本作の聴きどころは間違いなくこの1曲で、ピンク・フロイドの最高の1曲に挙げる人も多い名曲です。是非静かな部屋で明かりを消してこの1曲を聴いてみてください。静寂の中で最初にピーンと響く音は、ジャケットのように耳に響く1音かもしれないし、潜水艦の中に響くソナー音かもしれないし、深海や宇宙空間を漂うなかで見つけた明かりを表現したのかもしれない。想像力を掻き立てる音は、静かな空間の中で一音一音響き渡ります。そしてハモンドオルガンを中心に、幻想的なメロディの反復によって世界を広げていきます。上っ面をなぞるだけだとひたすら退屈なこの楽曲は、一度その世界に浸ることができれば、暗闇の中を手探りするような、サイケデリックに彩られた幻想空間のような不思議な世界の長旅を体験できます。11分半頃から、ぼやけた静かな空間を引き裂くような、イルカの鳴き声のような高音が突如現れます。カラスの鳴き声ような音も。そして再び、オープニングと同様の音が静かな空間に響き渡り、ベースとドラムが徐々に迫って少しずつ盛り上がっていきます。ラストに向けてダークさとヘヴィさが加わり、緊張感が高まります。そして歌メロが入りひと時の穏やかさが訪れ、またも緊張感を伴いながら、最後は上昇するかのようにフェードアウトしていきます。この長い音楽世界の旅路を聴き終えた後の充実感は凄まじいです。
音響効果で不思議な世界を作り出す本作は、『狂気』以前のピンク・フロイドの作品群では傑作です。特に23分半の大作「Echoes」は圧巻で、長い旅路へと誘います。
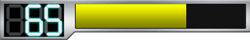
1972年 7thアルバム
バルベ・シュローダー監督の映画『La Vallée』のサウンドトラックです。ピンク・フロイドは既に『狂気』のレコーディングに入っていましたが一時中断し、本作の制作に至りました。
隠れ名盤という言葉がぴったりな作品で、地味ながらも良い楽曲が溢れています。ちなみにヒプノシスによる不思議なジャケットアートは、木に登って手を伸ばす男が、木漏れ日によってぼんやりと写って幻想的な写真になったのだそうです。
オープニングを飾る表題曲「Obscured By The Clouds」はインストゥルメンタル。リック・ライトのシンセサイザーと、デヴィッド・ギルモアのギターが主導します。ギターが切ない雰囲気の、ややダークで浮遊感のある楽曲です。続く「When You’re In」もインスト曲ですが、前曲より輪郭が明瞭でハキハキしています。「Burning Bridges」でボーカル入りとなりますが、リードボーカルはギルモアとライト。アンニュイでダウナーな雰囲気ながらも安心感を覚える温かさは、ピンク・フロイドならではの個性でしょう。「The Gold It’s In The…」は明るくノリの良い、ロック色の強い1曲です。金切音を立てるギターソロはご機嫌。アコースティックギターが美しい「Wot’s… Uh The Deal?」は爽やかで、そして切ないメロディ。シンプルなサウンドにギルモアの優しいボーカルが染み入ります。後半のメロウなエレキギターも良い。そしてダウナーなインスト曲「Mudmen」で、憂鬱ながらメロウな演奏に癒されるのです。泣きのギターも素晴らしい。
アルバム後半の幕開けとなる「Childhood’s End」は、ペタペタしたベースとキュンキュン鳴るギターに乗せて、ギルモアの歌が響きます。「Free Four」はロジャー・ウォーターズがボーカルを取る1曲です。愉快な曲調で、後半のギターの弾け具合は次作の名曲「Money」に通じるものがあります。歌詞では戦死した父親に言及しており、後の『ザ・ウォール』や『ファイナル・カット』のモチーフが既に表れています。続く「Stay」はメロウでムーディな1曲。ライトがボーカルを取っています。そしてラストの「Absolutely Curtains」はやや不気味な合唱で締めます。
『おせっかい』と『狂気』という名盤に挟まれ、しかもサウンドトラックという位置づけなので正直これまでスルーしてきました。しかしある意味『狂気』のプロトタイプというか、『狂気』に通じるメロウな演奏はとても良い。強烈な1曲はないものの、アルバムトータルとしては魅力的です。
数多くの名盤を差し置いて聴くほどではありませんが、無視できないクオリティの高さです。
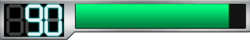
1973年 8thアルバム
米国のビルボード200に741週(15年間)に渡ってチャートインし続けたという、驚異のロングセラー。世界一のロングセラーアルバムとしてギネス記録にも載っています。当時、売上枚数計測の仕組みが各国で整っていなかったこともあり、総売上枚数については諸説ありますが、3500万枚とも5000万枚とも、あるいはそれ以上とも言われています。オーディオマニアが音響チェックのために「Speak To Me」の鼓動音を聴くので、そのために本作が売れるという話も聞いたことがあります。確かに、アルバム全体に散りばめられたSEを聴くだけでも、仕掛け満載で結構面白いです。全体的に陰鬱な雰囲気はあるものの、意外とキャッチーで聴きやすいです。
本作の特徴の一つに「全曲が繋がっている」というものも挙げられます(レコードのA面B面の都合で、「The Great Gig In The Sky」と「Money」の間に分断はありますが)。アルバム1枚で1つのストーリーを紡ぐというコンセプトアルバムの代表作としても挙げられます。
そして本作を魅力的なものにしている要素の一つに、ヒプノシスによるプリズムのジャケットアートがあります。ヒプノシスがいくつか案を提示したところ、メンバー満場一致でこのジャケットを採用したのだとか。
オープニングを飾る「Speak To Me」は小さな音で鼓動音とSEが散りばめられた小曲です。カラスのような鳴き声が聞こえた後、そのまま次曲「Breathe」になだれ込みます。浮遊感のあるムーディな楽曲で、妙な安心感があります。続いて「On The Run」では宇宙空間なのか道路なのか、どこかを高速で駆け抜けているような、反復される不思議な音。この音をベースに、いくつかの効果音が耳元を通り過ぎていきます。そしてドーンと爆発音が起きた後に、そのまま始まる「Time」。いきなり始まる時計のSEが強烈で、また間奏のデヴィッド・ギルモアのギタープレイも見事なのですが、それ以上に着目すべきはその歌詞でしょう。「ある日お前は10年の月日が過ぎ去っていたことに気づく 誰もいつ走ればいいのかなんて言わなかったし、お前はスタートのピストル音も逃したのだ」という一節が強烈に刺さります。時間は有限ということを強く感じさせます。そして「Breathe」のリプライズが流れた後に、レコードでいうA面ラスト曲「The Great Gig In The Sky」に繋がります。ゲストボーカルにクレア・トーリーを招き、リック・ライトの静かなピアノをバックに、ジャズ志向のメロウな雰囲気を演出します。
そしてレコードでいうB面は、レジスターや小銭のSEが印象的な「Money」で始まります。ロジャー・ウォーターズのベース音が刻むリズムを数えてみると7拍子という変なリズムを味わうことができます(中盤から4拍子)。プログレ界隈では変拍子は常套手段ですが、初めて触れると不思議な感覚に陥ると思います…私がそうでした。中盤のサックスもカッコいいですね。お金を「諸悪の根源」と歌いますが、妙なキャッチーさがあります。続く「Us And Them」はジャジーでしっとりとした楽曲です。最前線の兵士が死んでいくのに、将軍は地図上の黒と青(自軍か敵軍か)でしか見られないという歌詞に虚しさも感じます。サビでの歌唱もドラマチックですね。「Any Colour You Like」はインストゥルメンタル曲で、前半はキーボード主体、後半はギターが主体となります。サイケデリックな雰囲気が漂います。そして「狂人は心に」の邦題を持つ「Brain Damage」へ。不気味な笑い声がSEとして入るこの楽曲、歌詞で歌われている狂人とは薬物で狂ってしまった天才シド・バレットでしょうか。この楽曲の一節に「I’ll see you on the dark side of the moon」とアルバムタイトルが歌われています。そしてラスト曲「Eclipse」では、言葉を羅列した歌詞を歌いながら、徐々に盛り上がって壮大なクライマックス。そして鼓動音でフェードインしていくオープニング曲と同様に、鼓動音でフェードアウトして本作を終えます。
非常に聴きごたえのある作品です。じっくり聴かないと良さが分かりにくいピンク・フロイドの作品群の中では抜群に取っつきやすく、入門盤として最適な本作。次作以降は歌詞などのメッセージ性に重点が置かれ、シンプルなアレンジながらメロディと歌詞が重視されます。メロディに興味を持った方は本作から後の作品へ、様々な仕掛けによって作られる不思議な音響に興味を持った方は本作以前の作品へ遡ると、嗜好にあった素晴らしい作品に出会えると思います。















